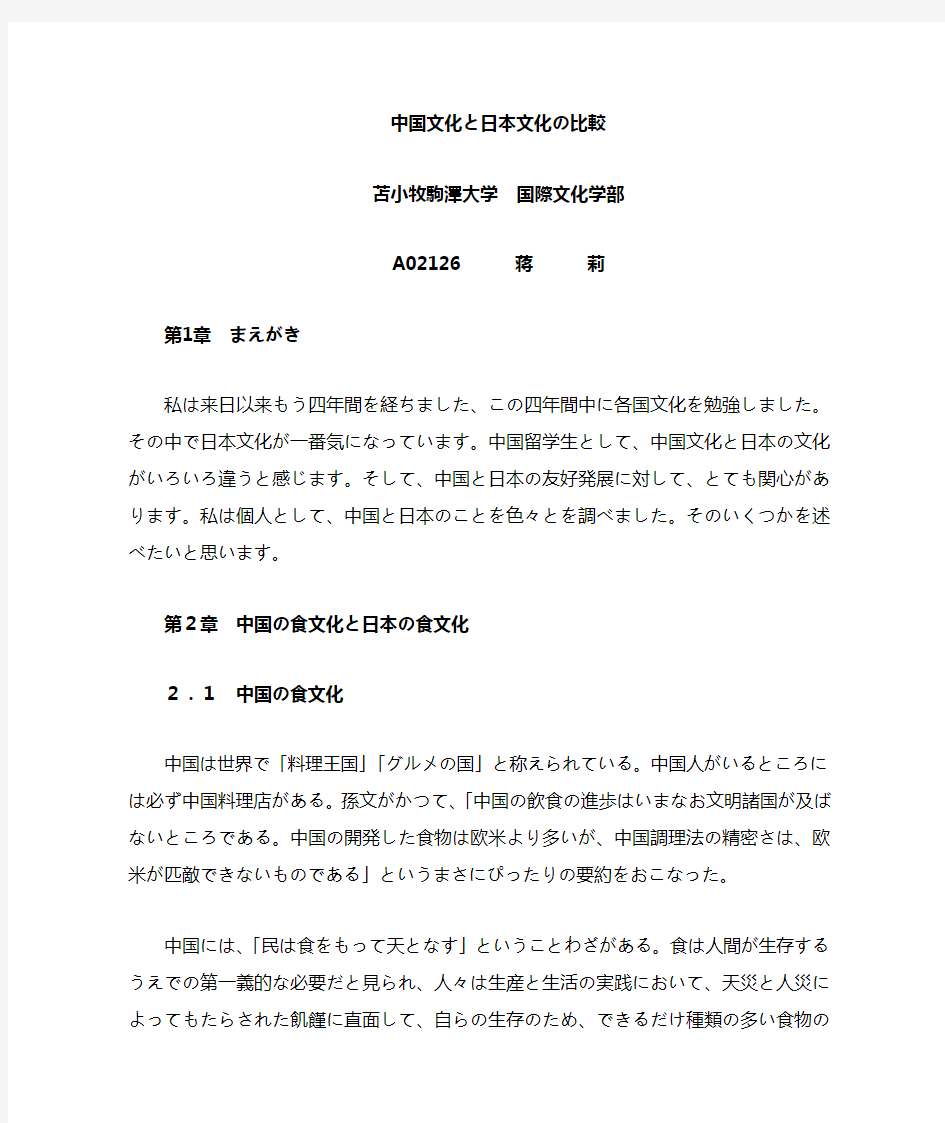
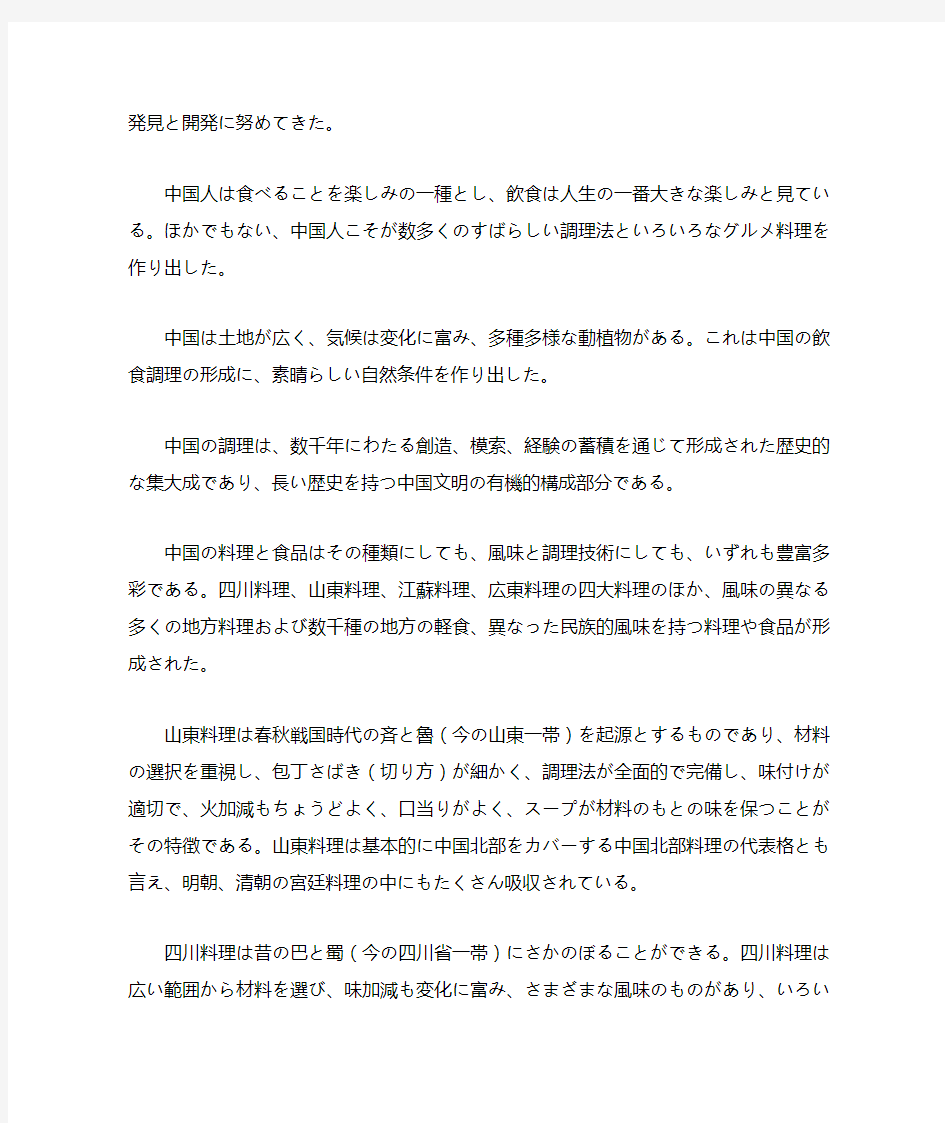
中国文化と日本文化の比較
苫小牧駒澤大学国際文化学部
A02126蒋莉
第1章まえがき
私は来日以来もう四年間を経ちました、この四年間中に各国文化を勉強しました。その中で日本文化が一番気になっています。中国留学生として、中国文化と日本の文化がいろいろ違うと感じます。そして、中国と日本の友好発展に対して、とても関心があります。私は個人として、中国と日本のことを色々とを調べました。そのいくつかを述べたいと思います。
第2章中国の食文化と日本の食文化
2.1中国の食文化
中国は世界で「料理王国」「グルメの国」と称えられている。中国人がいるところには必ず中国料理店がある。孫文がかつて、「中国の飲食の進歩はいまなお文明諸国が及ばないところである。中国の開発した食物は欧米より多いが、中国調理法の精密さは、欧米が匹敵できないものである」というまさにぴったりの要約をおこなった。
中国には、「民は食をもって天となす」ということわざがある。食は人間が生存するうえでの第一義的な必要だと見られ、人々は生産と生活の実践において、天災と人災によってもたらされた飢饉に直面して、自らの生存のため、できるだけ種類の多い食物の発見と開発に努めてきた。
中国人は食べることを楽しみの一種とし、飲食は人生の一番大きな楽しみと見ている。ほかでもない、中国人こそが数多くのすばらしい調理法といろいろなグルメ料理を作り出した。
中国は土地が広く、気候は変化に富み、多種多様な動植物がある。これは中国の飲食調理の形成に、素晴らしい自然条件を作り出した。
中国の調理は、数千年にわたる創造、模索、経験の蓄積を通じて形成された歴史的な集大成であり、長い歴史を持つ中国文明の有機的構成部分である。
中国の料理と食品はその種類にしても、風味と調理技術にしても、いずれも豊富多彩である。四川料理、山東料理、江蘇料理、広東料理の四大料理のほか、風味の異なる多くの地方料理および数千種の地方の軽食、異なった民族的風味を持つ料理や食品が形成された。
山東料理は春秋戦国時代の斉と魯(今の山東一帯)を起源とするものであり、材料の選択を重視し、包丁さばき(切り方)が細かく、調理法が全面的で完備し、味付けが適切で、火加減もちょうどよく、口当りがよく、スープが材料のもとの味を保つことがその特徴である。山東料理は基本的に中国北部をカバーする中国北部料理の代表格とも言え、明朝、清朝の宮廷料理の中にもたくさん吸収されている。
四川料理は昔の巴と蜀(今の四川省一帯)にさかのぼることができる。四川料理は広い範囲から材料を選び、味加減も変化に富み、さまざまな風味のものがあり、いろいろな調理法に加えて料理の種類も多いという特徴がある。統計によると、現在、四川料理の種類はすでに五千種に達している。味が辛いのがその特徴である。四川料理は「一つの料理が一つの風味をもち、百種の料理が百種の風味を持つ」と称えられている。
江蘇料理は蘇州、揚州と南京(いずれも江蘇省にある)の地方料理が互いに補完し合い、溶け合って形成されたものである。江蘇料理は材料の選択が厳しく、作り方が細かく、調理法がユニークで、さっぱりした味で、塩と甘味の加減がちょうどいいし、また材料のもとの味を保つことを重視することがその特徴である。また、もう一つの特徴は料理の色彩、造型を重視し、観賞の価値がある。
広東料理は古代を起源としているが、体系としては明代と清代に形成されたものである。広東料理は発展の過程において、五嶺の南一帯の地域の特色を保つことを踏まえて、たえず北部のさまざまな料理と調理法から養分を吸収するとともに、西洋料理の作り方をも一部参考にし、それを吸収して、現在の広東料理を形成した。その主な特徴は材料の品種が多く、風味がユニークで、季節別の料理づくりを重視し、口当りがよく、柔らかい。調理法は広東地方の特色に富む。
中国経済の発展、人々の収入の増加につれて、食品の質も急速に向上している。観光業が急速に発展しているため、内外観光客が日増しに増えている。社会経済の発展によって、多くの流動人口が現われている。これらすべては中国の飲食調理業のこの上なく大きな発展を促している。
現在、四川料理、山東料理、江蘇料理、広東料理の四大料理体系は基本的に全国の各大中都市をカバーしている。各大中都市では、主導的地位を占めている四川料理、山東料理、江蘇料理、広東料理と地元の風味の地方料理があるほか、ユニークな特色をもつ潮州、東北、山西、台湾、湖北、湖南、海南などの地方料理およびモンゴル族、タイ族、朝鮮族などの民族料理もある。また、宗教的色彩を帯びた精進料理とイスラム料理および数多くの地方風味をもつ軽食もある。
北京~庶民の味宮廷の味~
中国料理の代表といわれる北京料理。それは中国各地の料理の集大成であり、また、庶民の味から宮廷料理にいたるまで、伝承を継承し、改良を重ねて質の高い食文化を形成してきた結果とも言える。本編では、北京料理の日常食から北京の著名な料理店の厨房まで徹底取材し、それらの魅力を探る。
広東~食は広州に在り~
四季を通じて、樹木の濃い緑と花々の赤に彩られる広州。自由市場の多彩な食品の紹介に始まり、広州最大の料理店?渓酒家では、飲茶の風景に仔ブタの丸焼き
の全プロセスを撮影。单園酒家ではとうがんの蒸しものに代表される「蒸す」という東アジア独特の調理文化にスポットをあてる。
江单~魚米之郷の名菜譜~
米と魚介類が豊かな、魚米之郷?江单。本編では、とれたての魚と豊富な穀類の並ぶ鎮江の自由市場、楼外楼の伝統的な魚料理、上海の小籠包子やカニにカメラを向ける一方、紹興酒、鎮江香醋、金華火腿(ハム)など、中国随一と称されるものも取材し、江单全体の豊かな食文化の世界を紹介する。
四川~天府之国の百菜百味~
冬は比較的温暖、夏は盆地特有の酷暑。こうした風土を持つ四川は、香辛料や大豆食品をうまく複合させた充実した食文化を形成した。これら独特の四川料理の魅力を取材するほか、地の恵み?塩、水の恵み?野菜、さらに家常菜(家庭料理)にもカメラを向け、四川の食、生活、風土を詳しく紹介する。
中国の人々は中国在来の料理や食品をよく賞味しているが、異国情調に富む外国の風味も排斥しない。北京を例にあげてみよう。北京ではアジアのタイ、インドネシア、ベトナム、日本、韓国の風味のレストランのほか、フランスの風味とロシアの風味のレストランもあり、町のあちこちでハンバーガー、ピザ?パイ、ケンタッキ?フライド?チキンなど西洋軽食店を見かける。中国の飲食調理業の発展をいっそう促すために、中国の飲食調理業経営者は外国の調理技法とその他の長所を吸収し、参考にしている。
2.2日本の季節と食文化
端午とは月の初め(端)の午の日のことで,5月に限ることではないが,中国の漢代以後,5月5日を端午というようになった。日本の端午の節句の行事は,中国伝来のものが多く,それに日本古来の習俗などが加わって,病気や災厄をはらう目的の行事となった。
江戸時代には,武家はいうまでもなく町方でも,7歳以下の男子のいる家では,5月幟を戸外に立て,兜人形を飾っていた.また鯉幟を立てることは天保のころに行われた.当時の鯉幟は紙で鯉の形をつくり,竹の先につけて立てたもので,明治の末ごろにもまだ紙鯉が凧絵師によって作られていた。
食べ物としては,柏餅,粽(ちまき)があるが,江戸時代から江戸は柏餅,京坂は粽が主で,この傾向は現在も続いている。
粽は古くは茅の葉でまいたところから茅巻(ちまき)と呼んだのが語源と言われている。その歴史がとても古く,日本では10世紀始めには作られている。
柏餅は比較的新しく,江戸時代の寛永年間に作られ始めたとされている。もっとも,草木の葉で包んだり,巻いたりした菓子は古くからあり,その始めは「源氏物語」にかかれている”つばめもち”だと言われている。
うなぎの蒲焼き(時期7月、土用の丑の日)
江戸時代の、神田のうなぎ屋で春木屋善兵衛という人がいました.ある夏のこと、藤堂という大名家から「旅にでるので、蒲焼きをたくさん欲しい」という注文を受けました.そこで春木屋は、土用の子、丑、寅の3日間にわたってうなぎを焼き続け、その日毎に土かめにわけて入れておきました. さて約束の日にうなぎを取り出してみると、子の日と寅の日に焼いたうなぎは、色、味とも変わっていたのに、丑の日に焼いたものは、色、味、香りとも変わっていない。そこでそれを大名に納めました.それ以来、うなぎの蒲焼きは「丑の日」がよいということになったそうだ。
月見だんごなど(時期旧暦8月15夜と9月13夜)
十五夜の行事は中国で始まり、平安時代に日本に伝わり宮廷の月見の席では月の詩や歌を作り、雅楽を奏でたそうだ。江戸時代になると、多くの人々の間にも月見が広まり、だんごや枝豆、里芋、栗、柿、すすきなどを供えるようになった。十五夜は「仲秋の名月」または「いも名月」といわれ、主に里芋を供えて食べていた。また、十三夜を「後の名月」、「豆名月」といい枝豆を供えて食べていたようだが、現在では月見だんごが主になっている。
千歳飴(時期11月15日9)
七五三は,子供の成長を祝う行事だ。七五三では,千歳飴を食べる。千歳飴は,江戸時代の初め,浅草で飴売り八兵衛という人が「千年アメ」と名づけて売ったのが始まりといわれている。
千歳飴は水飴を適度に煮詰めた後,飴の中に気泡を入れながら加工した物で,このために色は白くなり,量も増え,風味がよくなります.赤く着色した物と組み合わせて紅白の飴を,長寿を願って鶴や亀が描かれた袋に入れる。
かぼちゃ(時期12月下旪)
冬至は1年中で一番昼が短い日だ。この日は,太陽がもっとも单にくるときだ。これから先は,また,日が長くなっていく。
世界の各国では,冬至を太陽の誕生日と考えるところが多く,これがお正月やクリスマスにつながっている。冬至にはかぼちゃを始め,おかゆやこんにゃくを食べる習慣が残っている。
一部の地方では,レンコン,みかんなど,「ん」のつく食べ物を7種類食べると幸福になれるともいわれる。これは冬になり,めずらしくなった野菜をお供えする意味からきている。
また,風邪をひかないよう,ゆず湯に入る習慣もある。寒いときは,かぼちゃ,にんじんなど色の濃い野菜を食べ,風邪の予防をするといった昔からの知恵が感じられる。
年越しそば(時期12月31日)
年越しそばは,江戸中期からの風習であろうとされ,江戸後期には地方によっては欠かせない物であった.由来鎌倉時代に中国から博多に来ていた貿易商が七百年ほど前に,年の瀬も越せない貧しい人たちにそばがき餅をふるまったところ翌年からみな運が向いてきたので,大晦日に運そばを食べるならわしが生じた.そば切りは細く長いので,長寿や身代が長く伸びるようにと食べた.そばは,新陳代謝をよくし体内を洗浄するので大晦日に食べて新年を迎える。
現在,「そば」といえば穀物でもあり麺でもあり区別しにくいが,江戸時代には麺のそばはそば切りとよんだ。穀物のそばは中国の雲单省が発祥地と言われており,日本でも奈良時代には既に栽培されていた。古くは粒食されていたようで,現在でも徳島県の山村には「そば米」があり,山形県には「むきそば」がある。これらは殻がついたままのそばの実を塩水でゆでて,殻の口が開く頃に取り出し,むしろの上でよく干してから脱穀したものである.粉食されるようになってからは,そば掻,そば餅などとされ,そば切りが現れたのは慶長年間(1596~1615)のことである.
第3章中国と日本の首都のくらし比較
中国国内のそれほど多くの地方を旅行したわけではないが、それでも1泊以上した場所の数は北京も含めて16か所になる。最近ではどの街に行っても、なんとなくどこも同じような感じに思えてあまり新鮮味を感じなくなってしまった。中国の街についてどこでも共通して当てはまる言葉がある。それは「雑然としている」ということである。東京や大阪だって雑然としているのは同じだが、日本の場合、歴史のある地方の都市に行くと、なんとなくしっとりと落ち着いた感じを受ける場合があるが、中国の場合、地方の小さな街へ行っても、小さいなら小さいなりに雑然としている。好意的に言うと「庶民の活気があふれる」とか「親しみの持てる」とかいう形容詞がつくわけである。どこへ行っても活気がある、人間の生活臭がある、というのは悪いことではない。
北京もそうした中国の街の一つである。市の北東部にある北京空港から市内までの約30kmの道はほとんど一直線で切れ目なく緑の街路樹が続いている。市内に入ると、まず第3環状路と交差するが、この交差点は北京の中でも一番立派な立体交差になっていて、まわりには最近建てられたばかりのアパ-ト群が並んでいる。このため、初めて中国へ来て、空港から第3環状路に入りそのまま合弁ホテルに入ってしまうと「へ~っ。中国っていうのも中々整然としたところですね。」という感想を抱くのである。もっとも、中国系の(合弁ではない)ホテルにあるこの事務所に来る人は、合弁ホテルに泊まる人よりは、もうちょっと「庶民的な雰囲気」に触れることができるわけである。「庶民の活気がみなぎる」朝夕の自転車通勤風景も「親しみの持てる」「生活臭のあふれた」自由市場の雰囲気も、好むと好まざるとに拘らず、経験することができるのである。
行政区域としての北京市はかなり広い。北京原人の発見された周口店や万里の長城のある八達嶺なども全て北京市内である。北京市の「市」とは、東京の場合の「都」と同じだと考えればよい。この周辺部も含めた北京市の人口は975万人、市街地部分だけの人口は655万人である(1986年末現在)。年平均気温は11.5度(東京は15.3度、以下()内は東京の値)、1月の平均気温-4.6度(+4.7度)、8月の平均
気温24.4度(26.7度)、年間降水量644mm(1,460mm)、年間日照時間数2,780時間(1,942時間)(いずれも1951年~1980年の平均)。冬尐し寒くなりすぎることを除けば北京は気候的には暮らしやすい街である。人口密度は580人/平方km(東京は奥多摩地区や伊豆諸島を含めても5,402人/平方km)。生活する上で東京よりは相当に楽である、はずである。しかし、実際にはそうではない。
経済の発展の程度が違うのだから、東京と北京を比較するのは無意味な話だが、気候や人口の話が出たついでに事実だけを書いて置くことにする。まず、北京には日本の大都市にあるJRや私鉄の電車に相当するものが全くない。地下鉄が環状線と東西線の2路線あるだけである。路面電車もない。あるのはバスとトロリ-?バスだけである。市民は地下鉄?バス?トロリ-バスに乗るか、そうでなかったら自転車で通勤する。東京で山の手線と中央線を除いて他のJR線と私鉄を全てなくしてバスしかない状況を想定してみれば、これが大変なことであることがわかるだろう。北京がこれでなんとかやっているのは自動車が尐ないからである。北京の自動車の数(軍用を除く)は184,503台で東京の20分の1である(東京は3,655,721台)。しかもこのうち自家用車(外国企業、外国人駐在員が所有しているものも含む)は5,122台しかない(数字は北京が1986年、東京が1987年3月31日現在)。通勤による車のラッシュはないのである。それが証拠に、北京でも月曜日の午前中は車の渋滞が起こることがあるが、それは8時前後ではなく、各事業所が活動を開始した後の10時ごろである。ほとんどの人が自転車通勤だが、自転車による通勤距離はせいぜい15kmくらいが限度である。それ以上だと北京には坂道がないとはいってもかなりしんどい。北京市当局は現在郊外にどんどん立派なアパ-ト群を建てているが、設備が充実しているわりにはあまり人気がないそうだ。それは時間通りに運行されないバスに乗るのも嫌だし、1時間以上かけて自転車で通勤するのもきついかららしい。公共交通機関が発達していないのも北京の発展にとっては大きな足枷である。
もう一つ北京で暮らしていて気が付くのは、人口が多い割にはデパ-トなどの集まった繁華街や銀行等の公共機関が尐ない、ということである。北京の繁華街としては、北京飯店のすぐ東側にある有名な王府井(ワンフ-チン)やこれと対称位置の北京市中心部の西側にある西卖(シ-タン)、古くからの老舗が多い前門(チェンメン)がある。「繁華街」と言えるのはこれくらいである。しかもこれらも「繁華街」とは行っても700~800mの道の両側に店がならんでいるだけである。デパ-トとしては王府井に北京百貨大楼(4階)がある程度である。これら3つの地区のほかにも天橋百貨公司など結構大きなデパ-トはあることはあるが、それでもやはり東京と比較するのは気の毒である。東京の場合、銀座、新宿、渋谷、池袋などいくつかの繁華街があって、それぞれに巨大なデパ-トが5つも6つもある。今、北京にいて考えると信じられないほどである。
北京は、中国の中でも、人口の割には商業面が発達していない街で、商品の数も種類も尐ない、と北京市民はぼやいている。確かに、北京は政治都市であって、買い物をするには不便なところである。北京市民は知り合いが出張で上海や広州へ行くと聞くと、お金を渡してセ-タ-やTシャツを買って来てもらう。彼らに言わせると、北京のファッションは「ダサイ」のだそうである。そういえば、この間桂林に行った時、その中心街にあるデパ-トへ行ってその品数の豊富さと内部の雰囲気のモダンさにびっくりしたことがある。北京にはああいう「ナウい」店はない。北京から同行
していった中国側の人が自分のサンダルか何かを買っていた。何も2,000kmも離れた桂林くんだりまで行ってサンダルを買うことはないと思うのだが、北京の店の「ダサさ」を考えたら買いたくなる気持ちもよくわかる。桂林は人口30万程度の小さな地方都市だが、観光地で外国人も多く来るから、アカぬけた感じになるのだろう。もっとも、その桂林の「品数豊富な」デパ-トでも、日本の、例えば「イト-ヨ-カド-武蔵境駅前店」に比べたら完全に負けてしまう。北京に住んでいると「せめて東京の近郊の駅前にあるデパ-トが一つでいいから北京にあったらなあ。デパ-トが無理なら小さなコンビニエンス?ストアでもいいから、いつでも新鮮な商品が豊富にある店があったらなあ。」という思いが切実なものとなる。
公共的な施設も尐ない。鉄道のタ-ミナル駅も北と单へ行く場合は北京駅一つしかない(北西の方向へ行く場合は西直門駅という別のタ-ミナルがある。近郊の短区間の列車や貨物のためには別のタ-ミナル駅がある)。東京で言えば東京駅と上野駅が一つになったようなものである。完全に処理能力の限界を超えている。切符売り場もこの駅の1か所しかないから、切符を買うにはいつも「艱難辛苦」に耐えなければならない。出口と入り口も1つづつしかない。列車が着くたびに出口は重い荷物をもった人々が殺到して大変な騒ぎになる。その変わり「5時の汽車で着くんだけど、出迎えは八重州側?丸の内側?丸の内なら北口、中央口、单口?」などと確認する必要はない。北京駅で出迎える、といったら1か所しかないのだから。
中国民航の航空券を買えるところも、国際郵便局も1か所しかない。外貨(日本円など)を貰おうとしたら空港の銀行以外では中国銀行本店の1か所しかない。個人の費用を日本から送金して貰っている人がお金を受け取る場所は、阜成門にある中国銀行本店の2階ロビ-の5番、6番窓口1か所しかないのである。だから、中国銀行では知り合いの日本人によく会う。日本人駐在員は北京に1か所しかないその場所に行かないと日本からの送金を受け取れないからである。北京では外国人は「知っている人に会わずにひっそりと暮らす」というのはほとんど不可能である。
銀行などが1か所しかないのに、それはそれでなんとかみんなうまくやっているのは、北京における経済活動がまだそれで十分な程度にしか発達していない、ということを表している。国際郵便局が1つで済んでいるのもその例の一つである。外国からの郵便小包みはごく小さいものを除いて全て建国門にある国際郵便局に届けられるが、各家まで配達はしてくれないから、受け取り人は各自で国際郵便局まで取りに行く。窓口は1つしかないが、多くの受け取り人が殺到してどうしようもない、ということはない。国際郵便小包みの量が人口9百万の北京市でも窓口が1つあればそれで十分な程度なのである。
国際郵便局だけでなく、市内電話の料金を支払う窓口も1つしかない。事務所の電話の電話基本料金と国内通話料金は毎月市内電話局(国際電話を扱う長途電話局というのは別にある)に支払いに行くが、窓口の人はもうこちらの事務所の名前を覚えていてこちらが顔を出すと領収書の束のなかから当事務所の分を引き出してくれる。見ると領収書の束はせいぜい数十枚しかない。電話料金は銀行口座からの自動引き落としにしている会社が多いからかも知れないが(当事務所も国際電話料金の方は銀行口座からの自動引き落としにしている)、それにしても首都北京に1か所しかない市内電話局としては、なんとなくさびしい感じである。田舎の電話局みたいに、窓口へ行って「やあ○○さん、お元気?」などと言われるような雰囲気も、素朴でいいもんだが、中国の電話の普及率がまだこの程度なのか、と思うと若干溜
め息が出る。
第4章中日の橋比較
4.1中国の橋
中国の人なら大抵知っている橋がある。それは山西山脈のふもとにある安済橋(俗に趙州橋と呼ばれる)である。この橋は隋の開皇中期(595-605)に河北省趙州の河に架けられた橋で、現存する最古の石製アーチ橋である。これを設計したのは隋代の工匠の李春という人物である。彼は橋梁技術に大きな改革を行い、従来の橋の考え方に革命をもたらした。設計と工事が厳格であるため頑丈で堅固であり、洪水や地震にも耐えてきた。その仕事の見事さは現在でもみることが出来る。
1400年も昔の橋がいまでも壊れないで残っているというのは、考えれば大変なことだ。昔の建物というのは、日本も中国もその他の国もそうだが、堅固で強い。今残っているのは、自然災害や戦乱にも耐えて残った希有な建築物であるけれど、それにしてもすごい。ギリシャで大地震が起きたときも、近代的な建物はバタバタ倒れたけれど、アテネ神殿はビクともしなかったらしい。日本にも法隆寺など、世界最古の木造建築が残っている。先日、法隆寺に行き、その建物を身近で見て、木はこれほど強いものだったのか、と驚かされた。
もう一つ、中国の人なら大抵知っている橋がある。单京にかかっている单京大橋だ。これはソ連の技術者が作り始めたが、中ソ関係が悪くなると引き揚げてしまったため、中国独自で作ることになった橋である。当時の中国の科学技術の象徴的存在であった。でも、私はなんとなく李春の橋の方がずっと残るような気がする。もっともっと何百年も。
4.2日本の橋
日本の古い橋は木で造られていた。山梨県大月市にある猿橋は、崖の両岸から角材を突き出しその上に橋桁が載っている構造で610年頃架けられたといわれているが、現在のものは1984年に再建されたものだ。岩国市にある錦帯橋は世界でも珍しい木造の連続アーチ橋で1673年に建造され1953年に復元された。猿橋、錦帯橋と越中の愛本橋(代りに木曽の桟橋という説もある)を日本の三奇橋と称されている。九州に数多くみられる石造アーチ橋も、中国の僧如定が長崎の眼鏡橋を造ったのが最初といわれている。沖縄の石橋の歴史はもっと古く、伝来も長崎の石橋とは異なるといわれている。また、平戸の幸橋は当時オランダ商館があったため別名オランダ橋とも呼ばれている。そのため、石橋の技術はヨーロッパから伝来したという説もある。長崎の眼鏡橋の建設技術は、その後、長崎から熊本、大分、鹿児島に石造アーチの建設技術が広められた。ちなみに、石造アーチ橋として日本ではじめて重要文化財として指定されたのは長崎眼鏡橋ではなく諌早眼鏡橋です
日本の近代橋の歴史は、明治維新の文明開花と同時期にはじまりまった。明治期、最初はイギリスの技術を輸入し鋳鉄、錬鉄を用いた鉄の橋が建設された。八幡製鉄所の水瓶河内貯水池に架けられている南河内橋はドイツの技術の影響を受けている。日清戦争(1894)以降はアメリカの影響を受け、鋼製のトラス橋がつぎつぎと建設された。ちなみに、日本で最古の鉄の橋は明治元(1868)F.L.Borgerの設計による桁橋で、長崎の中島川の、現在の中央橋の所に架かっていた「鉄橋(くろがね橋)」だ。今はもう架け替えられて当時の面影はないが、わずかに高欄だけが残されている。長崎の中島川に架かる出島橋は、橋名板に
は「明治四十三年架」と記されているが、明治23年に架設された新川口橋が明治43年に移設されたもので、現在供用されている鉄製道路橋のなかでは日本最古のものだ。橋門構の隅に唐草の装飾があり、橋名板は蝙蝠(こうもり)の形をしている。関東大震災後の橋梁復興事業では技術的に大きく進歩した。特に隅田川に架かる鋼橋は高張力鋼が使用され、清洲橋、永代橋、勝鬨橋など独自の特色をもっている。近年、これらの橋は修復されライトアップされるなど、歴史的に価値ある橋として認知されている。この時期は大正デモクラシーといわれた時期だ。他の文化と同じように橋に対しても新しい技術を積極的にとり入れる気運があったのだろう。一方、第二次大戦後の混乱の中、とにかく「渡れればよい」というような機能性のみを追求した橋が数多く建設された。同じ敗戦国のドイツでは連合軍によって破壊された橋を元のまま修復したり、経済性の追求とともに美観的にも優れた斜張橋が開発されたりしている。近年、橋の景観?美観が注目されていますが、F.レオンハルト教授は50年前から景観?美観を考慮した橋の設計を行なっていると著``Bruecken''に書いている。
第2次大戦後の変遷は、新材料と新工法の開発とその使用、新しい構造形式と設計方法の開発にある。とくに橋の構造分野に大きく貢献したのは溶接性の改善と高張力鋼の開発だ。「鉄は国家なり」の政策の下、製鉄技術の進歩により、橋の建設技術も進歩した。今日、本州?四国連絡橋をはじめ多くの超長大橋が日本各地で建設されているが、このような技術開発があってからこそ実現可能となったのだろう。
第5章漢方をめぐる中日の比較
日本の漢方は初め朝鮮半島を通って日本に伝えられていた。奈良平安時代になると、遣唐使によって日本に伝えられたが、まだ庶民のものではなかった。鎌倉時代になると、やっと漢方医学も庶民のものとなった。室町時代には田代三喜(たしろさんき)などが中国に渡って、中国医学を持ち帰った。中国から伝えられた中国医学は曲直瀬道三(まなせどうざん)などによって発展していったが、鎖国によって外国との交流が尐なくなった江戸時代になると吉益東洞(よしますとうどう)を中心とした「古方派」と呼ばれる人達が「傷寒論(しょうかんろん)」という書物を基礎にして、日本独特の考え方をもった今の日本漢方の基礎を作った。明治以降、この流れを汲む湯本求真(ゆもときゅうしん)や大塚敬節(おおつかけいせつ)などが現在の日本の漢方を発展させた。
中医学と日本の漢方のもっとも大きな違いは、中医学が「黄帝内経(こうていだいけい)」を基礎として、陰陽五行などの理論を駆使して、病証を把握して、弁証していくのに対して、日本の漢方は、病理哲学的な理論を考えずに、直接症状から処方を考えていくのが特徴だ。このため中医学はどちらかというと理論的で、病気を治すということだけでなく、病気を予防したり、健康で長生きするための養生法なども重要視されてきた。
現代最も大きな違いは、現在中国では、中医学専門の大学を卒業した中医師といわれるお医者さんが沢山いることと、中医学専門の病院があることだ。日本漢方にも沢山の優れた点があるが、中医学の歴史、層の厚さ、現在の教育制度、一般の人の理解などを総合すると、やはり「中国」が本場であることを実感せざるにはいられない。
第6章中日関係の発展及び将来
今年は日中国交正常化26周年、日中平和条約締結20周年という日中関係史上、両国にとって記念すべき重要な年に当たる。この世紀の変わり目に、この間の日中関係を振り返り総括することは、21世紀に向けての長期、安定した日中関係をさらに推進し、打ち立てる上で極めて有益なことと考える。
6.1中日の政治経済協力について
26年前、日中両国の各界の友好人士が日中関係の発展を押し進めるために、長期間にわたり、たゆまない努力をしたことを背景に、両国の指導者と政治家達の先人は、卓越した見識をもって国交正常化実現のために政治的な決断を下し、重要な歴史的意義をもつ「日中共同声明」を発表し、日中関係の新たな一頁を開いた。20年前、両国はまた、「日中平和友好条約」を締結した。この二つの歴史的な文書は、両国の関係で遵守すべき基本原則を確立し、両国人民の子々孫々にわたる友好を維持し、発展させるための確固とした政治的な基盤を築いた。その後、永年にわたって、日中両国政府と人民は相い共に努力し、絶えず友誼を増進させ、政治、経済、科学技術及び文化交流等の各方面で急速な進歩と喜ぶべき成果を挙げることが出来た。両国の友好協力の関係は、日中二千年の往来の歴史上、かつてない広がりと深さと高まりを見せた。
政治の面についていえば、両国指導者は高い次元で、頻繁に相互訪問し、政府各部門の間では、さまざまな次元、ルートの協議、対話の機軸を作り上げた。双方は、また、「平和友好、平等互恵、長期安定、相互信頼」という日中関係四原則を打ち立て、「日中友好21世紀委員会」の設置に合意した。ここ数年来、両国指導者の往来はさらに頻繁になり、特に、1992年、江沢民総書記の訪日及び天皇、皇后両陛下の訪中は、両国と両国人民の友好関係発展をさらに押し進める上で重要な貢献をなすものであった。昨年、日中両国政府首脳の相互訪問が成功裏に実現し、そして、21世紀に向けての善隣友好協力関係の構築と子々孫々にわたる友好関係実現のために努力することに合意した。
1998年の11月、江沢民中国国家主席が国家元首として初めて日本を訪問した。訪問期間中、江沢民主席は、小渕恵三首相との間で、過去を総括する基礎の上に、未来に向けた両国の関係発展及び共に関心を寄せる国際問題について意見を交換し、重要な、共通の認識に達した旨の「共同声明」を発表した。これは、「日中共同声明」、「日中平和友好条約」に次ぐ、両国の関係発展をリードしていくための、3つ目の重要な文書である。これはまた、両国の関係が、新たな発展段階に入ったことを物語るものである。
経済面では、両国の協力関係は良好な形勢の中で急速に発展してきた。1996年、日中間の輸出入貿易の規模は、総額600億ドル余りに達し、1972年国交恢復当時の10.39億ドルの60倍以上になった。日本は、いまや、中国にとっての最大の貿易パートナーとなり、中国も日本の2番目に大きな貿易パートナーとなった。日本の対中投資も増加し続けた。1970年代末、日本の対中投資は、わずか0.14億ドルであったが、1996年末には、中国が許可した日本の中国における投資プロジェクトは、14,991件、協定金額にして263.8億ドル、実行投資金額は141.86億ドルとなり、日本は中国の第2の投資国となった。投資対象地区も、沿海州地区から次第に内陸へと展開された。また、直接投資の拡大は二国間貿易の増加を促し、投資の増加が貿易の発展を促すという好循環の形が形成された。円借款も、日中経済協力の重要な一面である。1979年から、日本は中国に対して政府借款を供与し、1995
年までに、計3回、累計金額は16,109億円に達した。これらは、64のプロジェクトに用いられた。1996-2000年の間に、第4次円借款を供与し、また、双方は1996年末、議定書に調印し、「3 + 2」方式で2回に分けて供与することになった。そのうち、1996年から1998年の3カ年に、日本は5,800億円を供与することになった。これらの借款は、主として、中国の交通、エネルギー、農業施設及び環境保護等の40の重点プロジェクトに用いられる。現在までのところ、日本政府が承諾した借款は、諸外国が中国政府に供与することを承諾した総金額の内の40%以上を占め、第1位である。極めて大きな実効をあげた上述の経済協力は、中国の現代化建設を促進しただけでなく、また、日本の経済発展にプラスになった。
文化交流の面では、日中両国政府は、1979年、文化協力協定に調印し、双方の文化交流には、いろいろなルート、次元、形式の、喜ばしい局面が現れた。日中双方の文化、教育、新聞、学術機構の相互訪問と交流が空前の活気を見せ、相互訪問の学者及び共同研究プロジェクトが日増しに増加した。両国の人事往来は、1972年、わずか9,000人であったが、1996年には延べ120万人に達した。両国間で結ばれた友好姉妹都市の数は、186に達し、中国が世界各国との間で締結した友好姉妹都市総数の約1/4を占める。これは、世界でもあまり例を見ないことである。
上記の事実だけでも、日中国交正常化後26年以来の巨大な成果を充分に物語るものである。これらの成果は、また、幾世代の人々の努力と心血を注いだ結果であり、正に得難いものであり、貴重なものである。「水を飲むとき、井戸を掘った人のことを忘れず」。われわれは、両国の幾世代にもわたって日中友好事業に関心を寄せ、支持してくれた人々に対し、永久に感謝し続けたい。また、歴史は、彼らのことを忘れることはないであろう。
6.2中日友好
日中善隣友好協力関係を発展させることは、両国人民の共通の利益に合致するばかでなく、アジア太平洋地域及び世界の平和を守り、この地域、乃至全地球が共に発展し繁栄することを促進する上で重要な意義を有する。
現在、国際状勢には、依然として多くの不安定な要素が存在している。しかし、平和と発展とは、時代の流れである。アジア太平洋地域の各国は、たとえ意識形態と社会制度が異なっているにせよ、みなが平和と発展を求めている。今後、アジア太平洋地域が、平和、安定、発展と繁栄の方向へ向かって行けるか否か、そのキーはこの地域の国家が積極的に努力し、協力するか否かにかかっている。中国は、最大の発展途上国である。日本は、アジアで唯一の発展国家であり、世界第2の経済大国である。日中両国が、アジア太平洋地域と国際社会の重要なメンバーとして、地域と国際協力を強化し、共同の発展を促進することは、アジアと世界の平和と安定のために、ともに重大な責任を背負っている。従って、独自の重要な貢献をなすべきである。明らかなことは、日中親善友好協力関係が前進し続けることは、両国人民に幸福をもたらすだけでなく、この地域及び世界の平和と発展に寄与するものであるということである。
20世紀が間もなく過ぎ、人類は21世紀を迎えようとしている。この重要な歴史的な時に当たり、どのような世界を次世代に残すべきか、国家間にはどのような関係が打ち立てられてこそ自国の根本的な利益にかなうのか、対話か対抗か、これらのことを各国とも真剣に考えている。この重大な問題は、現実として各国の目の前に
突き出されている。正に、このような時代背景があるからこそ、ここ数年来、国家の関係、特に、大国の関係に重大な調整がなされている。
昨年秋、江沢民主席が訪米し、今年の6月、クリントン大統領が訪中し、中米関係の発展目標と枞組みについての合意がなされ、「21世紀に向けての戦略的なパートナーシップを構築するために共に努力する」ことを取り決めた。江沢民主席とエリツィン大統領は昨年、相互訪問し、中ロ間に「21世紀に向けての戦略的パートナーシップ」を重ねて確認した。フランスのシラク大統領は昨年5月訪中し、両国の間で「21世紀に向けての全面的なパートナーシップ」締結を宣言した。また、最近、日中両国が発表した「共同声明」の中で、「平和と発展のための友好協力パートナーシップ関係の構築」を宣言した。
上記一連のトップの相互訪問と「パートナーシップ関係」は、冷戦後の大国の関係の調整が新たな段階に入ったことを示している。世界が多極化の方向へ進む中で、大国の間に競争や摩擦はあるが、しかし、いまや協力と協調が主流である。各国はみな、共同の利益の接点を求め合っており、関係の改善と発展が調整の主流となっている。また、調整の目標は、非同盟、非対抗、第三国を対象としないことをその特徴とする、新しい形の国家関係を構築することにある。そういう意味で言えば、調整は国際全体の状勢が引き続き緩和の方向へ進むのにプラスであり、平和と発展の歴史の潮流に沿うものである。
日中関係は、この一大潮流に適応すべきであり、また適応できるものである。協力関係を発展させ、互いに対抗せず、友好と協調を両国関係の基調としなければならない。これは、日中両国人民の共通の願いにマッチするばかりでなく、アジア太平洋地域各国人民の共通の願いにもマッチするものである。それは、日中両国が善隣友好協力を堅持することがアジア太平洋地域の安定にとって重要な基盤であり、この地域の平和と安全を維持し、守る上で大きなウェイトを占め、また、共同の発展と繁栄にプラスとなるからである。
日中貿易関係は、両国の友好協力関係における重要な一部分をなしている。両国の経済には、大きな補完性がある。中国が改革開放を堅持し、拡大して以降、経済は急速に発展した。また、中国は自然資源と労働力資源が豊かであり、マーケットのキャパシティーが大きい。一方、日本は世界で経済が最も発達している国家の一つであり、資金が豊富で、技術が進んでおり、管理の経験も豊かである。従って、日中両国が協力関係を強化し、互いに長所を補い、経済貿易関係をさらに進めれば、必ずや双方に巨大なメリットをもたらすことであろう。
現在、国際関係における経済の占める地位がますます高まるにつれて、経済安定の問題が日増しに際だって来ている。昨年発生した東单アジア金融危機は、多くの国家と地域へ波及したと同時に、世界の経済がグローバル化するプロセスでの各国の協調及び共に経済挑戦に立ち向かうという新たな課題を提起してくれた。日中両国は、アジアの大国として、協力関係を強化し、共同して東单アジア金融危機に対処すべきであり、アジア経済の恢復と振興のために相応の貢献をなすべきである。
現在の世界は、相互依存関係がますます明確になっている。日中両国はその必要性を共有し、共通の利益も広範囲のものになっている。中国が経済発展戦略を実現する上で日本の支持が必要であり、日本経済が引き続き発展するためにも中
国の協力が必要である。国際間の事務を処理し、国際危機に対処する面においても両国は努力して協調する必要がある。日中両国は、事実、すでに相当密接な相互依存関係を形成している。日中友好は排他的なものではなく、しかも、両国は幅広い国際関係を持っている。地域及び世界に対して、それぞれがウェイトと重要な影響力を持っている。従って、双方の友好協力と相互依存の関係は、日中両国のみにとどまらず、アジア太平洋地域と世界の平和、安定及び発展に対して計り知れない影響を及ぼすものである。
第7章おわりに
日中国交正常化26年来の発展過程を振り返えれば、日中友好関係の発展状況は、全体として、満足のいくものである。先人の期待にも添い、のちの世代への激励となろう。しかし、両国の関係では、紆余曲折もあったし、一部、見解の相違や問題もあった。現在、日中関係は、正に、歴史を継承し、未来を切り開く重要な歴史段階にある。両国関係の発展の中における正、反両面の経験教訓を正しく総括し、吸収することは、今後の日中関係の発展をリードしていく上で、重要な意味を持っている。
「日中共同声明」と「日中平和友好条約」は、日中関係正常化の礎であり、日中善隣友好関係を発展させる上での政治的基盤と法的根拠となるものであり、また、両国間に存在する問題を適切に処理する基準となるものである。26年来、日中関係の発展の歴史が示してしるように、声明と条約を真摯に遵守し、履行してこそ、両国及び両国人民に重要な利益をもたらすことが出来るのである。今後、国際状勢がどうのように変化しようとも、日中両国が共同してこの重要な文書の中で規定する原則を守り、声明と条約の中で規定する責任と義務を着実に履行して行きさえすれば、日中関係の発展の正しい方向を必ずや確保することが出来よう。
日中経済貿易関係は、日中関係全体の中での基盤である。26年来の実践が示すしているように、両国の経済貿易関係は、両国の政治関係の源であり、良好な政治関係は、また、両国の関係を発展させる重要な原動力である。今後とも、双方は経済協力を引き続き強化して行くべきであり、これまでの基盤の上に、さらに新しい土台を作り上げて行くべきである。
日中関係は現在、すでに二国間関係の枞を遙かに飛び越えている。両国は、地域と世界的な範囲から、また、長期的、戦略的な高所から、終始、正確に両国の関係発展の方向を正しく掌握し、日中友好という大局への干渉と妨害を回避しなければならない。双方は、国際事務の中での協調と協力をさらに押し進め、共同して世界の平和と人類の進歩の事業に力を致す必要がある。このことは、日中関係を発展させる新しい基盤であり、それは洋々たる前途を有する事業である。
日中青年の間の交流を強化し、さらに多くの、日中友好事業の後継者を育てあげることは、両国にとって極めて意義あるものである。「人は代り、時は移る」。時間の推移に伴って、かつて日中友好のために重要な貢献をした両国の古い政治家と各界の人士が相継いでこの世を去り、或いは引退した。如何にして、日中関係の後継者を養成するかは、今や急を要する問題である。日中関係は、来るべき21世紀が、健全に、安定して発展するには、両国の青年の間の各レベルでの交流を強化し、相互理解と信頼関係を増進し、両国友好の伝統を継承し、引き続き発揚させ
る必要がある。これは、百年の大計、千年の大計でもある。
未来を展望するとき、日中双方が相互尊重、小異を捨てて大同に着くという精神に基づいて、現在に立脚し、遠い未来に着眼し、両国関係の方向と大局を把握して行けば、日中関係の前途は明るいものである。日中善隣友好は、必ずや、日中両国人民に幸福をもたらし、世界の平和、そして発展と繁栄を促すことであろう。