中日の酒文化についての探究
- 格式:doc
- 大小:99.00 KB
- 文档页数:16
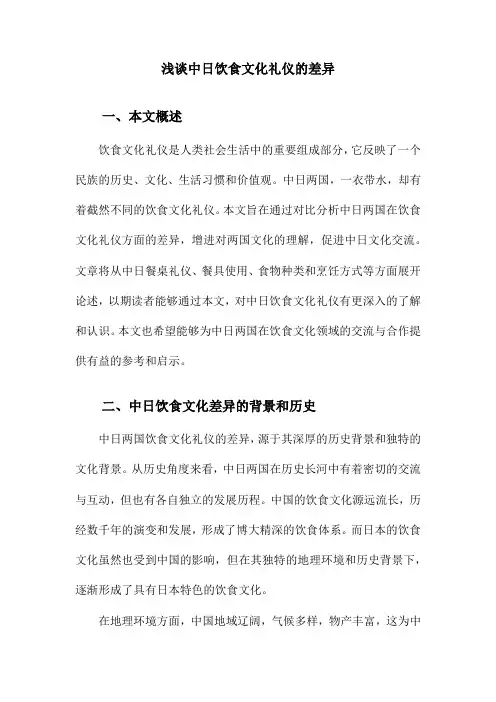
浅谈中日饮食文化礼仪的差异一、本文概述饮食文化礼仪是人类社会生活中的重要组成部分,它反映了一个民族的历史、文化、生活习惯和价值观。
中日两国,一衣带水,却有着截然不同的饮食文化礼仪。
本文旨在通过对比分析中日两国在饮食文化礼仪方面的差异,增进对两国文化的理解,促进中日文化交流。
文章将从中日餐桌礼仪、餐具使用、食物种类和烹饪方式等方面展开论述,以期读者能够通过本文,对中日饮食文化礼仪有更深入的了解和认识。
本文也希望能够为中日两国在饮食文化领域的交流与合作提供有益的参考和启示。
二、中日饮食文化差异的背景和历史中日两国饮食文化礼仪的差异,源于其深厚的历史背景和独特的文化背景。
从历史角度来看,中日两国在历史长河中有着密切的交流与互动,但也有各自独立的发展历程。
中国的饮食文化源远流长,历经数千年的演变和发展,形成了博大精深的饮食体系。
而日本的饮食文化虽然也受到中国的影响,但在其独特的地理环境和历史背景下,逐渐形成了具有日本特色的饮食文化。
在地理环境方面,中国地域辽阔,气候多样,物产丰富,这为中国的饮食文化提供了丰富的物质基础。
而日本则是一个岛国,自然资源相对有限,这在一定程度上影响了日本人的饮食习惯和食材选择。
例如,日本的海鲜料理就是其独特的地理环境所孕育出的饮食文化代表。
在文化背景方面,中日两国在哲学、宗教、审美等方面都有着不同的传统和观念。
例如,中国的儒家文化强调“和”与“礼”,这在一定程度上影响了中国人的饮食礼仪和餐桌文化。
而日本的茶道、武道等传统文化也对其饮食文化产生了深远的影响。
中日两国在历史上的交流和互动也对双方的饮食文化产生了影响。
例如,中国的唐朝时期,日本曾派遣大量遣唐使到中国学习,其中就包括饮食文化。
而近代以来,随着中日交流的增多,两国的饮食文化也开始相互融合和借鉴。
中日饮食文化礼仪的差异源于其深厚的历史背景和独特的文化背景。
了解和探究这些差异,有助于我们更好地理解和欣赏中日两国的饮食文化,促进两国人民之间的交流和友谊。
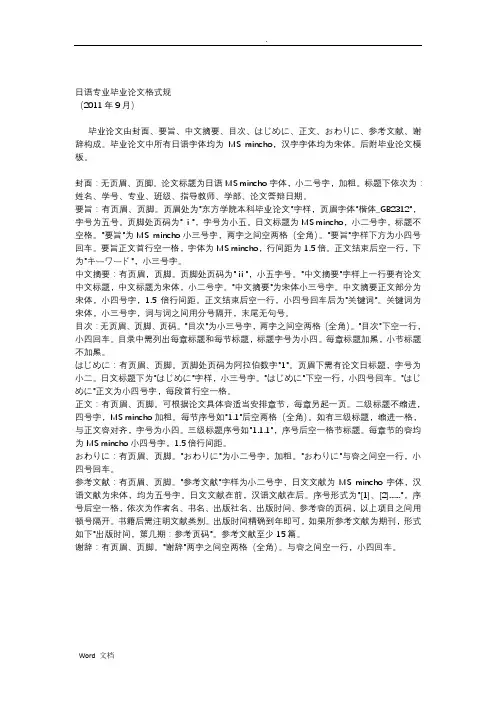
日语专业毕业论文格式规(2011年9月)毕业论文由封面、要旨、中文摘要、目次、はじめに、正文、おわりに、参考文献、谢辞构成。
毕业论文中所有日语字体均为MS mincho,汉字字体均为宋体。
后附毕业论文模板。
封面:无页眉、页脚。
论文标题为日语MS mincho字体,小二号字,加粗。
标题下依次为:姓名、学号、专业、班级、指导教师、学部、论文答辩日期。
要旨:有页眉、页脚。
页眉处为"东方学院本科毕业论文"字样,页眉字体"楷体_GB2312",字号为五号。
页脚处页码为"ⅰ",字号为小五。
日文标题为MS mincho,小二号字,标题不空格。
"要旨"为MS mincho小三号字,两字之间空两格(全角)。
"要旨"字样下方为小四号回车。
要旨正文首行空一格,字体为MS mincho,行间距为1.5倍。
正文结束后空一行,下为"キーワード",小三号字。
中文摘要:有页眉,页脚。
页脚处页码为"ⅱ",小五字号。
"中文摘要"字样上一行要有论文中文标题,中文标题为宋体,小二号字。
"中文摘要"为宋体小三号字。
中文摘要正文部分为宋体,小四号字,1.5倍行间距。
正文结束后空一行,小四号回车后为"关键词"。
关键词为宋体,小三号字,词与词之间用分号隔开,末尾无句号。
目次:无页眉、页脚、页码。
"目次"为小三号字,两字之间空两格(全角)。
"目次"下空一行,小四回车。
目录中需列出每章标题和每节标题,标题字号为小四。
每章标题加黑,小节标题不加黑。
はじめに:有页眉、页脚。
页脚处页码为阿拉伯数字"1"。
页眉下需有论文日标题,字号为小二。
日文标题下为"はじめに"字样,小三号字。


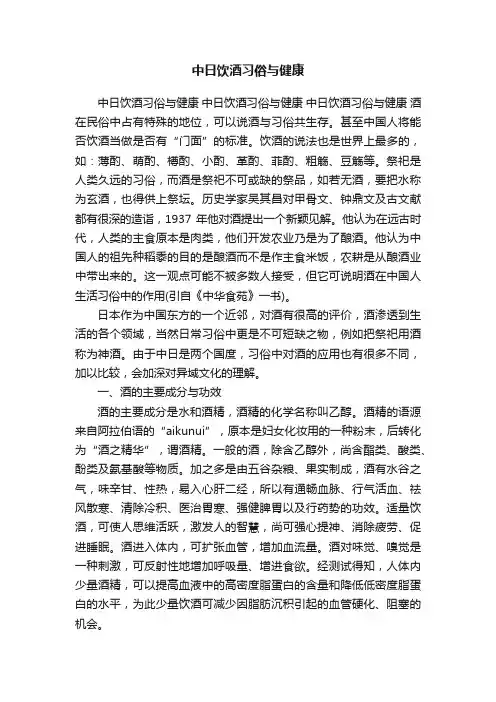
中日饮酒习俗与健康中日饮酒习俗与健康中日饮酒习俗与健康中日饮酒习俗与健康酒在民俗中占有特殊的地位,可以说酒与习俗共生存。
甚至中国人将能否饮酒当做是否有“门面”的标准。
饮酒的说法也是世界上最多的,如:薄酌、萌酌、樽酌、小酌、革酌、菲酌、粗觞、豆觞等。
祭祀是人类久远的习俗,而酒是祭祀不可或缺的祭品,如若无酒,要把水称为玄酒,也得供上祭坛。
历史学家吴其昌对甲骨文、钟鼎文及古文献都有很深的造诣,1937年他对酒提出一个新颖见解。
他认为在远古时代,人类的主食原本是肉类,他们开发农业乃是为了酿酒。
他认为中国人的祖先种稻黍的目的是酿酒而不是作主食米饭,农耕是从酿酒业中带出来的。
这一观点可能不被多数人接受,但它可说明酒在中国人生活习俗中的作用(引自《中华食苑》一书)。
日本作为中国东方的一个近邻,对酒有很高的评价,酒渗透到生活的各个领域,当然日常习俗中更是不可短缺之物,例如把祭祀用酒称为神酒。
由于中日是两个国度,习俗中对酒的应用也有很多不同,加以比较,会加深对异域文化的理解。
一、酒的主要成分与功效酒的主要成分是水和酒精,酒精的化学名称叫乙醇。
酒精的语源来自阿拉伯语的“aikunui”,原本是妇女化妆用的一种粉末,后转化为“酒之精华”,谓酒精。
一般的酒,除含乙醇外,尚含酯类、酸类、酚类及氨基酸等物质。
加之多是由五谷杂粮、果实制成,酒有水谷之气,味辛甘、性热,易入心肝二经,所以有通畅血脉、行气活血、祛风散寒、清除冷积、医治胃寒、强健脾胃以及行药势的功效。
适量饮酒,可使人思维活跃,激发人的智慧,尚可强心提神、消除疲劳、促进睡眠。
酒进入体内,可扩张血管,增加血流量。
酒对味觉、嗅觉是一种刺激,可反射性地增加呼吸量、增进食欲。
经测试得知,人体内少量酒精,可以提高血液中的高密度脂蛋白的含量和降低低密度脂蛋白的水平,为此少量饮酒可减少因脂肪沉积引起的血管硬化、阻塞的机会。
酒的功效异常广泛,酒既是一种独特的物质文化,也是一种形态丰富的精神文化。
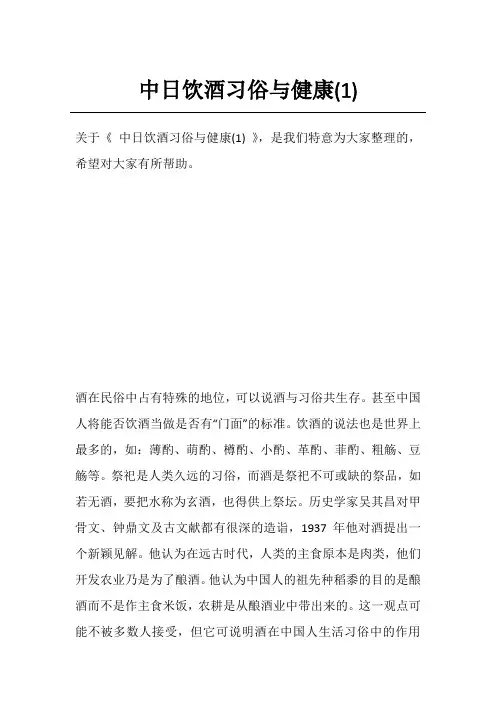
中日饮酒习俗与健康(1) 关于《 中日饮酒习俗与健康(1) 》,是我们特意为大家整理的,希望对大家有所帮助。
酒在民俗中占有特殊的地位,可以说酒与习俗共生存。甚至中国人将能否饮酒当做是否有“门面”的标准。饮酒的说法也是世界上最多的,如:薄酌、萌酌、樽酌、小酌、革酌、菲酌、粗觞、豆觞等。祭祀是人类久远的习俗,而酒是祭祀不可或缺的祭品,如若无酒,要把水称为玄酒,也得供上祭坛。历史学家吴其昌对甲骨文、钟鼎文及古文献都有很深的造诣,1937年他对酒提出一个新颖见解。他认为在远古时代,人类的主食原本是肉类,他们开发农业乃是为了酿酒。他认为中国人的祖先种稻黍的目的是酿酒而不是作主食米饭,农耕是从酿酒业中带出来的。这一观点可能不被多数人接受,但它可说明酒在中国人生活习俗中的作用(引自《中华食苑》一书)。 日本作为中国东方的一个近邻,对酒有很高的评价,酒渗透到生活的各个领域,当然日常习俗中更是不可短缺之物,例如把祭祀用酒称为神酒。由于中日是两个国度,习俗中对酒的应用也有很多不同,加以比较,会加深对异域文化的理解。
一、酒的主要成分与功效 酒的主要成分是水和酒精,酒精的化学名称叫乙醇。酒精的语源来自阿拉伯语的“aikunui”,原本是妇女化妆用的一种粉末,后转化为“酒之精华”,谓酒精。一般的酒,除含乙醇外,尚含酯类、酸类、酚类及氨基酸等物质。加之多是由五谷杂粮、果实制成,酒有水谷之气,味辛甘、性热,易入心肝二经,所以有通畅血脉、行气活血、祛风散寒、清除冷积、医治胃寒、强健脾胃以及行药势的功效。适量饮酒,可使人思维活跃,激发人的智慧,尚可强心提神、消除疲劳、促进睡眠。酒进入体内,可扩张血管,增加血流量。酒对味觉、嗅觉是一种刺激,可反射性地增加呼吸量、增进食欲。经测试得知,人体内少量酒精,可以提高血液中的高密度脂蛋白的含量和降低低密度脂蛋白的水平,为此少量饮酒可减少因脂肪沉积引起的血管硬化、阻塞的机会。 酒的功效异常广泛,酒既是一种独特的物质文化,也是一种形态丰富的精神文化。酒的主要功效有解乏、提神、助兴、调味、待客、引发诗情画意等,在此将主要的加以说明。
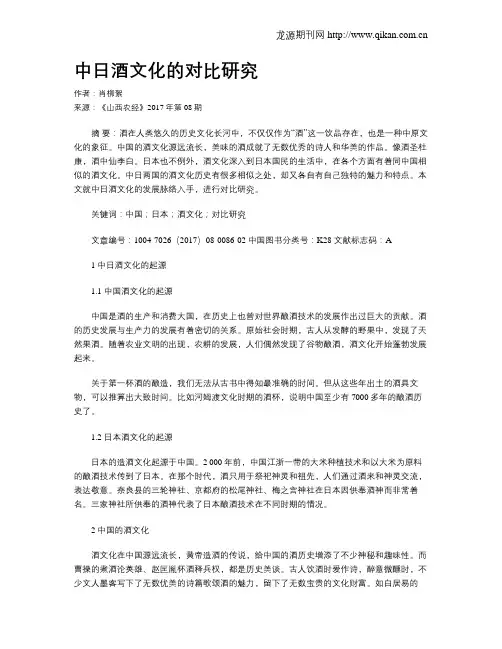
中日酒文化的对比研究作者:肖柳絮来源:《山西农经》2017年第08期摘要:酒在人类悠久的历史文化长河中,不仅仅作为“酒”这一饮品存在,也是一种中原文化的象征。
中国的酒文化源远流长,美味的酒成就了无数优秀的诗人和华美的作品。
像酒圣杜康,酒中仙李白。
日本也不例外,酒文化深入到日本国民的生活中,在各个方面有着同中国相似的酒文化。
中日两国的酒文化历史有很多相似之处,却又各自有自己独特的魅力和特点。
本文就中日酒文化的发展脉络入手,进行对比研究。
关键词:中国;日本;酒文化;对比研究文章编号:1004-7026(2017)08-0086-02 中国图书分类号:K28 文献标志码:A1 中日酒文化的起源1.1 中国酒文化的起源中国是酒的生产和消费大国,在历史上也曾对世界酿酒技术的发展作出过巨大的贡献。
酒的历史发展与生产力的发展有着密切的关系。
原始社会时期,古人从发酵的野果中,发现了天然果酒。
随着农业文明的出现,农耕的发展,人们偶然发现了谷物酿酒,酒文化开始蓬勃发展起来。
关于第一杯酒的酿造,我们无法从古书中得知最准确的时间。
但从这些年出土的酒具文物,可以推算出大致时间。
比如河姆渡文化时期的酒杯,说明中国至少有7000多年的酿酒历史了。
1.2 日本酒文化的起源日本的造酒文化起源于中国。
2 000年前,中国江浙一带的大米种植技术和以大米为原料的酿酒技术传到了日本。
在那个时代,酒只用于祭祀神灵和祖先,人们通过酒来和神灵交流,表达敬意。
奈良县的三轮神社、京都府的松尾神社、梅之宫神社在日本因供奉酒神而非常着名。
三家神社所供奉的酒神代表了日本酿酒技术在不同时期的情况。
2 中国的酒文化酒文化在中国源远流长,黄帝造酒的传说,给中国的酒历史增添了不少神秘和趣味性。
而曹操的煮酒论英雄、赵匡胤杯酒释兵权,都是历史美谈。
古人饮酒时爱作诗,醉意微醺时,不少文人墨客写下了无数优美的诗篇歌颂酒的魅力,留下了无数宝贵的文化财富。
如白居易的“绿蚁新醅酒,红泥小火炉。
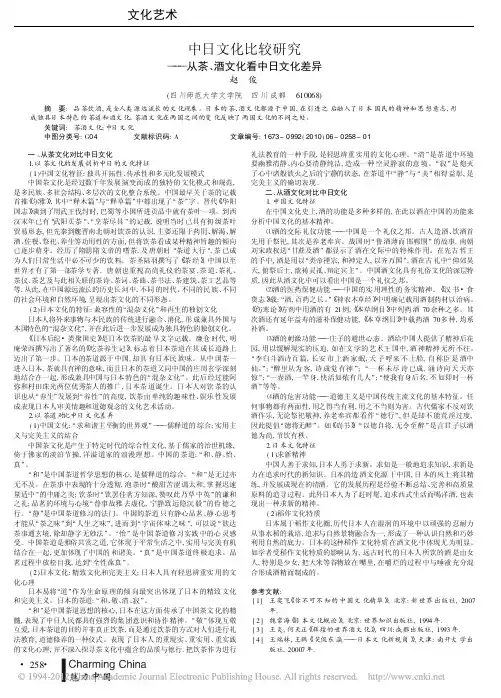
中日文化比较研究)))从茶、酒文化看中日文化差异赵俊(四川师范大学文学院四川成都610068)摘要:品茶饮酒,是全人类源远流长的文化现象。
日本的茶、酒文化都源于中国,在引进之后融入了日本国民的精神和思想意志,形成独具日本特色的茶道和酒文化,茶酒文化在两国之间的变化反映了两国文化的不同之处。
关键词:茶酒文化;中日文化中图分类号:G04文献标识码:A文章编号:1673-0992(2010)06-0258-01一、从茶文化对比中日文化1.以茶文化的发展剖析中日的文化特征(1)中国文化特征:独具开拓性、传承性和多元化发展模式中国茶文化是经过数千年发展演变而成的独特的文化模式和规范,是多民族、多社会结构、多层次的文化整合系统。
中国最早关于茶的记载首推5尔雅6,其中/释木篇0与/释草篇0中都出现了/茶0字。
晋代5华阳国志6谈到了周武王伐纣时,巴蜀等小国所进贡品中就有茶叶一项。
到西汉末年已有"武阳买茶"、/烹茶尽具0的记载,说明当时已具有初级茶叶贸易形态,但先秦到魏晋南北朝对饮茶的认识,主要还限于药用、解渴、解酒、佐餐、祭祀、养生等功用性的方面,但将饮茶看成某种精神旨趣的倾向已逐步萌芽。
经历了隋朝隋文帝的嗜茶,及唐朝时"茶道大行",茶已成为人们日常生活中必不可少的饮料。
茶圣陆羽撰写了5茶经6,中国以至世界才有了第一部茶学专著。
唐朝也重视高尚礼仪的茶宴、茶道、茶礼、茶仪、茶艺及与此相关联的茶诗、茶词、茶曲、茶书法、茶建筑、茶工艺品等等,从此,在中国源远流长的历史长河中,不同的时代、不同的民族、不同的社会环境和自然环境,呈现出茶文化的不同形态。
(2)日本文化的特征:兼容性的/混杂文化0和再生的独创文化日本人将外来事物与本民族的传统进行融合、消化,形成兼具外国与本国特色的/混杂文化0,并在此后进一步发展成为独具特色的独创文化。
5日本后纪#类聚国史6是日本饮茶的最早文字记载。
廉仓时代,明庵荣西撰写出了著名的5吃茶养生记6,标志着日本茶道在其成长道路上迈出了第一步。
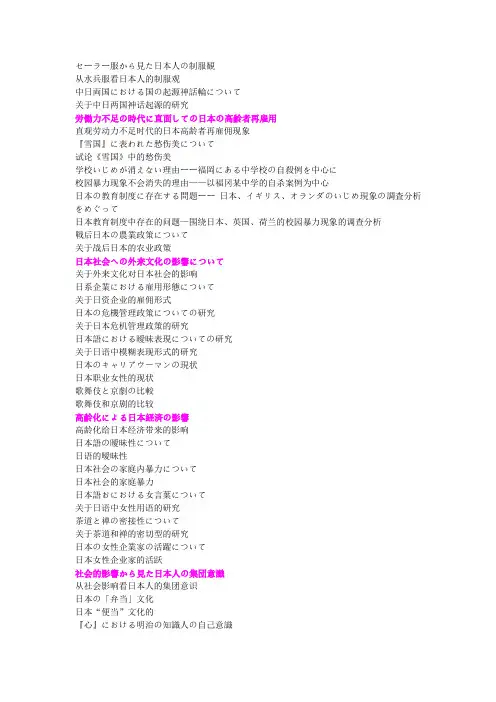
セーラー服から見た日本人の制服観从水兵服看日本人的制服观中日両国における国の起源神話輪について关于中日两国神话起源的研究労働力不足の時代に直面しての日本の高齢者再雇用直观劳动力不足时代的日本高龄者再雇佣现象『雪国』に表われた愁伤美について试论《雪国》中的愁伤美学校いじめが消えない理由ーー福岡にある中学校の自殺例を中心に校园暴力现象不会消失的理由——以福冈某中学的自杀案例为中心日本の教育制度に存在する問題ーー日本、イギリス、オランダのいじめ現象の調査分析をめぐって日本教育制度中存在的问题—围绕日本、英国、荷兰的校园暴力现象的调查分析戦后日本の農業政策について关于战后日本的农业政策日本社会への外来文化の影響について关于外来文化对日本社会的影响日系企業における雇用形態について关于日资企业的雇佣形式日本の危機管理政策についての研究关于日本危机管理政策的研究日本語における曖昧表現についての研究关于日语中模糊表现形式的研究日本のキャリアウ―マンの現状日本职业女性的现状歌舞伎と京劇の比較歌舞伎和京剧的比较高齢化による日本経済の影響高龄化给日本经济带来的影响日本語の曖昧性について日语的暧昧性日本社会の家庭内暴力について日本社会的家庭暴力日本語おにおける女言葉について关于日语中女性用语的研究茶道と禅の密接性について关于茶道和禅的密切型的研究日本の女性企業家の活躍について日本女性企业家的活跃社会的影響から見た日本人の集団意識从社会影响看日本人的集团意识日本の「弁当」文化日本“便当”文化的『心』における明治の知識人の自己意識从《心》看明治时期知识分子的自我意识日本人の自殺心理日本人的自杀心理日本のドラマから見られた中日文化の差異从日本电视剧看中日文化差异日本人の危機意識について――国民の環境保護意識を中心に关于日本人的危机意识——以其国民的环保意识为中心日本の少子化対策について关于日本少子化对策的研究日本企業における「残業」の意義关于日本企业中“加班”现象的意义日本人特有の「以心伝心」について关于日本人特有的“以心传心”现象的研究日本の派遣社员の行方―日雇い派遣を例として日本派遣员工的去向——以临时短期员工为例中小企業と戦后日本経済の飛躍―「松下」の発展を辿って中小企业与战后日本经济的腾飞—探索松下的发展雇用形态多様化の动向―非正规労働者を中心に以非正式劳动者为中心——论雇佣形态多样化的动向現代における中日貿易の摩擦―農産物を中心に以农业品为中心——论现代中日贸易的摩擦日本自動車工業の再発展―環境問題から考える日本汽车工业的重振——从环境问题思考中国化粧品の将来性――資生堂の戦略から学ぶ展望中国化妆品企业——借鉴资生堂的策略アイドルの社会的影響――ジャニズ事務所を中心に以杰尼斯事务所为中心——论偶像的社会影响日本茶道文化の発展から見た独自性从日本茶道文化的发展看其独特性日本マンガの影響について关于日本漫画的影响中日国民の環境保護意識について――ゴミ処理の視点から从垃圾处理方面分析——论中日国民的环保意识茶道の礼儀作法から見た日本人の階級意識从茶道的礼仪看日本人的阶级意识中日文化における牛のイメージの違い中日文化中“牛”概念的差异能と京劇の表現形式に関する比較研究关于能和京剧的表现形式的比较研究宫崎骏の『となりのトトロ』から見た日本人の自然観从宫崎骏的《龙猫》看日本人的自然观芸能文化の保存と丧失ーー芸者を中心に演艺文化的保存和丧失——以艺者为中心日本料理から見た生食文化从日本料理看生食文化日本語における省略表現について论日语中的省略表现法中日両国における女性の職業観――家庭主婦の例から見て中日两国女性的职业观——以家庭主妇为例日本人の職場意識について论日本人的工作意识相撲の未来について有关相扑未来的发展宮崎アニメの日本社会への影響宫崎骏动漫对日本社会的影响中日两国の色彩の象徴性について――「赤色」を中心に有关中日两国颜色象征性——以“红色”为中心動物に関する中日ことわざの対照研究中日动物谚语比较研究着物に見られた日本人の美意識从和服看日本人的审美观「てしまう」の使い方についての研究有关“てしまう”的用法研究日本人口の減少化について关于日本人口减少化的研究中日文化の差異による貿易摩擦中日文化差异对贸易摩擦的影响集団主義から個人主義への変貌从集团主义到个人主义的变更中国と日本の酒文化について关于中国和日本的酒文化研究日本语と中国语の同じ言叶で违う意味の単语源氏物语と红楼梦贵族社会の相违点夏目漱石(日本人の作家なら谁でもいい)のある作品から日本人の考え方日本の少子化问题と中国の一人っ子政策民主党と中国政策の展望受験制度の比较非行化生徒の実态と対策日本の文化を通しての日本人のものの考え方ごみ问题中国と日本の比较とこれからの展望日本の若者の考え方日本の若者の言叶食品问题から両国间のあり方中国、日本の交流の歴史(ある人物、事件を通して)20までいきませんが、日本人、日本の文化はいろいろありますので、ことばの说明に関する考察~国语辞典を资料として~强调を表す语についての研究「喜び」の表现に関する考察味の表现に関する考察ものの名前とその名づけに関する考察现代语における「全然」の用法女性の文末形式に関する研究同意を求める「~だろう」の使用~日本语母语话者と日本语学习者の比较~日本语会话教科书におけるあいづちの表现日本语教科书における终助词の扱い谢罪の表现とその使用意识に関する考察若者ことばの特徴オノマトペと动词の共起性に関する调査回避ストラテジーに関する考察现代日本语における自称词、他称词の使用に関する研究原因、理由を表す「から」「ので」に関する一考察终助词「ね」の意味机能「必ず」と「きっと」の意味分析受动文の使用と意识に関する一考察前置き表现に関する一考察日语自动词在表达中的作用从受授动词看日本人的人际关系中日委婉表达的差异从日语中的待遇表现看日本人的语言观念从年轻人用语看日本青年人的价值观从近年来流行语的发展看当今日本社会对日本人姓名的考察对日本地名的考察日本的雨和风与日本人的季节感日本语言中的美意识考察中日家庭成员之间称呼的比较中日青年就职观念的差异日本的少子化问题考察日本女性就业状况的变化从日本人的饮食生活看欧美文化的影响对日本社会中欺凌现象的考察对日本浴室文化的考察自杀与日本的岛国文化从“花”看中日美意识的差异日本人生活里的“和”意识成语翻译技巧研究中日口译中的语境研究论中日互译中母语对译文的影响文学翻译中人物形象与语境的依存关系中文歇后语与顺口溜的日译研究关于日语拟声、拟态词的汉语翻译关联翻译理论在文学翻译(或口译)中的应用中日谚语对比与翻译研究议中日谚语的互译技巧论中日商标翻译互译技巧研究中日商业广告用语、广告词的互译技巧研究论翻译中信、达、雅的关系论翻译中的直译与意译论中日翻译中的语义对等问题中日口译中的语境的处理技巧中文(或中日)新词、流行词日译(或互译)研究“まで”和“までに”の応用の分析“ないで”和“なくて”の応用の分析“たら”“ば”“と”“なら”の応用の分析“にとって”和“にたいして”の応用の分析苏州シルク输出品の実态の分析无锡の陶器输出品の実态の分析常州のトランクス输出品の実态の分析南京の服装输出品の実态の分析南通蒲団输出品の実态の分析翻訳の质と言叶遣いの関系について分析走れメロスの天気について描写の私见伊豆の踊子の人物の心理描写について日本の自然主义文学の特徴についてー≪破戒≫などから)≪伊豆の踊子≫と≪舞姫≫の人物运命の比较大江健三郎の作品の特徴について川端康成の作品の特徴についてメロスの信念の强さから考えたこと日本语翻訳方法と理论の検讨“信达雅”翻译理论の応用翻译の质と历史资料の関系について.doc村上春树小说中的女性解读——以青春三部曲为例论村上春树小说中的寻找意识——以《寻羊冒险记》为例论宫崎骏动画中“飞行器”之意象芥川龙之介与其周围的女性——关于芥川之死从《地狱变》看芥川的艺术观论芥川龙之介中国题材作品群的思想倾向论芥川早期文学中“火”之意象芥川龙之介与《聊斋志异》从芥川的《鼻子》看日本人的羞辱观论日本战后“社会派”文学的“政治性”论川端康成文学中“镜”之意象从川端康成的《雪国》看日本传统美学意识川端康成《雪国》三种中译本评析汉语“被”字句及其日译研究中日指示词的比较研究日语高年级学生「ている」误用研究文脉指示中“その”的汉译日语“夕”和汉语“了”的对照研究从电影译名看外来文化对中日两国语言的影响关于日语流行语的研究关于日语惯用句(从结构或语义分析角度)关于日语惯用句(从中日文化对比角度)关于日语惯用句(从中日惯用句比较角度)关于日语惯用句(从翻译角度)关于含有某一特定汉字的日语惯用句(从结构或语义分析的角度)关于含有某一特定汉字的日语惯用句(从中日惯用句比较角度)关于含有某一特定汉字的日语惯用句(从翻译角度)关于日语成语(从中日比较的角度)关于日语成语(从语义和结构分析角度)关于日语成语(从翻译的角度)关于日语谚语(从文化的角度)关于日语谚语(从翻译角度)关于日语新闻翻译关于日语程度副词关于日语陈述副词关于日语敬语关于日本人的表现心理关于日语的特质关于中日交流中的跨文化交际关于石川达三及其作品日汉指示代词对比研究关于「ようだ」「そうだ」「らしい」的比较有关“こと”和“の”的分析比较关于身体词汇惯用句的日汉对比对日语中的请求表达的考察关于自动词与他动词的研究关于补助要素“てある”和ている的考察汉日成语谚语对比研究汉日拟声词拟态词的对比研究有关授受表现日中对照研究日语中汉字的读法汉日被动句型对比研究日中敬语表达对比研究从日语外来词的变迁看日本社会格助词“に”的意义用法及其它关于日语中的女性用语赏樱花和日本人的自然观关于中日老龄化问题日本企业文化和宗教信仰中国和日本的食文化在语言中的表现中国文化对日本茶文化的影响日本女性婚姻观的变迁形成日本少子化的主客观成因探索日本动漫对世界的影响论日本文化中开放性与主体性特征关于日本文学中的美意识日本文学中的唯美主义日本和歌文学芥川龙之介小说研究无常观与日本文学从芥川的“鼻子”透析芥川的人生观从日语的暧昧表现探讨日本人的性格日语自动词的意义分析汉日成语谚语对比研究日语惯用句论日语的呼应表达日语敬语研究日语拟声拟态词研究日语授受表现研究日语教学中文化导入问题研究中日惯用句表现之比较研究日本语の敬语误用と敬语意识关于日语头部身体词汇惯用句日语敬语的现状与将来中日同形词的对照研究从敬语表达看日本人的敬语意识汉日敬语的比较分析论《细雪》中妙子的自由追求.日中敬语表达对比研究日本人的死生观中日敬语对译研究“とても”与“很”的比较研究从“虫がいい”看日本人的语言技巧日语动物谚语及其汉语译文的对比研究日本语における拟态语拟声语について日本语に入った外来语について日本语の「しゃれ」について日本语の「なぞなぞ」について日本语の国字(和字)について日本语における隠语について现代日本语の中における江戸言叶日本人の略语の作り方五七调と七五调の诗学「小呗」と「どどいつ」の音乐性枕词はなぜ五文字なのか?和歌に及ぼした中国汉诗の影响松尾芭蕉に与えた汉诗の影响日本人の汉诗汉俳について「於母影」、「海潮音」、「月下の一群」における翻译态度比较论夏目漱石と正冈子规の往复书简日本人の书简の文体と作法日本人が咏じる植物倾向日本人の苗字について子供の命名に见られる日本人の特性流行歌流行语に见られる日本人の心性日本的隠者と中国的隠者日本の庭园と中国の园林日本人の世间体(体面)と中国人の面子日本人と中国人のマナー感觉日本の幽灵と中国の鬼について日本の妖怪変化について日本の山贼と海贼について星の民间传承における中国人日本人の宇宙观比较论道教が日本の民俗生活习惯に及ぼした影响について古代中国音乐が雅乐に及ぼした影响について绘巻物に见られる日本人の庶民生活について江戸时代の锁国の功罪について江戸时代の教育について日本の驿辨について日本人の遵法意识(ルール遵守感觉)日本人のペットの饲い方について日本人の笑い古代日本人の恋爱と结婚日本人の地狱观と极乐观日本文化における「间(ま)」について现代日本人の服饰に见られる色彩倾向现代日本人の「粹」と「野暮」日本的风狂の精神とは何かおたくとマニア「萌え」とは何か虚无僧と山伏について「山窝」について「心中」について「じゃんけん」の地域性について日本人はなぜ水に流したがるのか?日本人はなぜ空气を读むことを气にするのか?なぜ宦官は日本に入ってこなかったのか?车内放送における日本人の世话意识车内で平然と化妆をする日本人女性の感觉新闻杂志の讽刺漫画に见られる日本人の政治社会性みそみりんしょうゆにおける日本食文化の特徴日本におけるゴミの分别とリサイクルなぜ日本卓球は中国卓球に胜てないのか?中日同形语の比较/中日同形词的比较中日両国语助数词の异同/中日两国量词使用的差异日常挨拶の中日比较/日常寒暄语的中日比较拟音拟态语の中日対照/拟声拟态词的中日比较日中同形语「的」についての比较/关于中日同形汉字“的”的对比中国语と日本语における外来语の比较/汉语和日语中的外来语比较中日両国语人称代名词の比较分析/中日两国人称代词比较分析自然に関する中日惯用句の比较/中日自然惯用语的比较日本语における婉曲表现/浅析日语中的委婉表达日本语における感情表现用语の特质について/日语情感表达用语特点的分析日本语における条件表现/浅析日语中的条件表现日本语における思いやり表现/关于日语中的体贴式表达日本语における「雨」の表现について/浅析日语中与“雨”相关的表达日本语における「汉字语汇」意味の変迁/浅析日语中汉字词汇含义的变迁日本语における男女の言叶遣いの区别/日语中男女用语的差别日本语の惯用句の文法的特徴について/浅析日语惯用句的语法特征日本语における外来语の発展について/试论日语中外来语的发展日本语の女性语の特徴分析/日语中女性用语的特征分析暧昧语の表现から见る日本语の特性/从暧昧语看日语的特点日本语における第二人称の表现/浅析日语中第二人称的表现方式从语言表达看日本人的心理特征日语的模糊现象究因试谈日语的暧昧表达与语境的依存关系谈日语口语中几个常见的暧昧表现日语的间接语言行为浅谈日语的“受身形”表达方式关于格助词:“に”和“と”关于终助词“ね”关于“は”和“が”关于“だろう”关于日语中的否定表达论日语中的人称代词论中日第一人称代词汉日第二人称对比研究主语省略现象的日汉对照以《刺青》为例看谷崎润一郎的美意识谈谷崎润一郎作品中的女性形象略论耽美主义作家的美学观非母语环境下暧昧表达习得之实证分析非母语环境下も的习得情况之实证分析非母语环境下た的习得情况之实证分析非母语环境下ている的习得情况之实证分析非母语环境下まで的习得情况之实证分析非母语环境下に的习得情况之实证分析非母语环境下で的习得情况之实证分析非母语环境下ばかり的习得情况之实证分析非母语环境下が的习得情况之实证分析非母语环境下ハシル与カケル的习得情况之实证分析非母语环境下モドル与カエル及ヒキカエス的习得情况之实证分析非母语环境下トオル、トオス、ツウジル的习得情况之实证分析夏目漱石作品中的女性形象——以《我是猫》和《明暗》为例谈川端康成作品中的女性形象日语交际用语中的暧昧表现中日礼貌语言对比研究论日语中的人称代词初探日语拟声拟态词的特征从文化的视点看日语中的省略表达浅论日语中的委婉表达试论日本语中的敬语误用和敬语意识汉日成语谚语对比研究日语敬语的现状与将来日语被动态的汉译及其问题论日语高级视听课之日本电影及电视剧欣赏课论“气”字惯用词组的语义特征和建构中国人日语学习中的误用分析议日语汉字和日本文化的关系中日被动句的对比研究关于日本语中的否定表达的探讨日本姓名的文化内涵从外来词的吸收看日本社会和文化关于日语中的女性用语关于日语流行语的研究通过“寒暄”观察日本的文化特点日本食の中国语表记について日本企业の中国名について中日の同形异义语について中日の鱼の名前の违いについて中国の省略语、日本の省略语汉字使用圏の比较日本の常用汉字の追加について日本から中国に来た汉字について中国と日本の色のイメージ中国と日本の食文化の违い日本と中国のタブーの违い日本の平均寿命の高さを考える日本の晩婚化、少子化を考える日本の社会保障制度-特に年金制度を中心に-日本のオーバードクター问题日本人の宗教観日本の外来语についてカタカナ表记はすべて外国のものか奈良平安期の日本人留学生について前四史における日本の记事について宪法十七条と中国の史书古代日本人の好きな花-万叶集と古今和歌集の歌から-织田信长、豊臣秀吉、徳川家康の比较孙文の盟友梅屋庄吉について「大地の子」に见る残留日本人孤児の研究2009年の政変について-自民党政治の终焉-日本の终身雇用の崩壊と派遣制度日本の农业について-特に自给率の低さを中心に-阪神淡路大震灾とその复兴について日本の昔话と中国の昔话「源氏物语」から见た平安贵族の生活「枕草子」から见た平安时代の女性の生活鲁迅の留学について日本の葬式を考える-映画「おくりびと」から-宫崎骏のアニメに见る日本人と环境日本の国技相扑における外国人の进出について少林寺拳法について日本の地震対策について日本の温泉について-地域分布とその成分-日本人の中国语学习者について日资企业里的跨文化交际研究日语报纸新闻标题的关联理论解释中日合资A&D公司的跨文化冲突日本在华独资企业的文化研究日汉语言表达方式差异及跨文化交际日本人的内外意识与集团意识关于我国企业导入日本企业文化的几点思考日本企业文化的特色及其启示日本在华企业人力资源管理研究关于在华日资企业“日本式经营”的文化分析日本在华企业雇佣制度的文化分析在华日资企业内部沟通研究日本式人事管理给我们的启示第八代雅阁在中国市场的SWOT分析代雅阁:喧嚣背后——解读广州本田的营销战略日本三大汽车制造商的中国市场营销战略丰田——了解顾客做新车(市场调研)独具特色的丰田营销管理日式管理的精髓——“持续改进”在华中小日企“本土化”过程中的问题与对策——以长三角地区为例日资企业中高层管理人员本土化滞后因素研究依靠品质管理创造顾客价值——日本朝日啤酒公司个案分析日本强势汽车品牌的形象传播丰田生产方式在吉汽公司的应用研究日本汽车新产品开发策略分析一汽丰田汽车销售有限公司渠道策略研究丰田“威驰”营销策略研究大连中升雷克萨斯汽车销售4S店服务营销战略研究古今和歌集的恋歌古今和歌集的四季歌日本茶道及其文化内涵日本国民性的特征从和歌看日本人的审美观表现禅与茶道日本的武士道浅论古今和歌集的恋歌与闺怨诗论《细雪》中妙子的自由追求对日语中的请求表达的语用考察日本人的死生观中日敬语对译研究从谚语来看日本人的传统家庭文化日语敬语的现状与将来日语被动句的考察日语动漫语言特色之浅见日语新词汉译译法类型探讨汉语新词日译译法类型探讨日语二重表记新发展初探中日网络语言差异研究文字以外的语言方式探索1(图形语言)文字以外的语言方式探索2(肢体语言)文字以外的语言方式探索3(符号语言)文字以外的语言方式探索4(声音语言)文字以外的语言方式探索5(视觉语言)文字以外的语言方式探索6(信号语言)格助词「を」非宾语用法研究日本人取名新动向特点探索中日贸易前景分析方法探讨日本公司及店家晨会作法的几种类型中日大学毕业生求职程序差异中日公司内部处理上下级关系的不同日语能力测试对实际语言应用的作用探讨学校的日语学习与工作的日语需要结合情况之我见男生与女生在外语学习上的差异与原因探索日本传统与现代的统一与和谐日本语学习动机日本人好きな言叶と日本文化日本人の好き嫌いについて日本の学校教育における问题(いじめ、不登校など)日本の小学校英语教育と中国小学校英语教育の比较アルバイトについて中日大学生の比较死に対する日本人の意识日本の子どもの自立性中日の年金制度の违う就职にあって日中意识の违う日本语の暧昧表现について日本の食文化の特徴『ノルウェの森』から见る村上春树の文化特徴和制英语について花见と日本人自然観日本の温泉について日本の名字について日本の祭りの文化日本语の受身と中国语の受け身日本语を教える时に日本文化の导入日语和汉语的相互影响日语学习动机日语词汇どうも的词义分析及其应用关于日语汉字的研究关于现代日语中[ものの]与「ものを」的用法考察从外来词的吸收看日本社会和文化日语学习策略调查研究对在日语句子主部中的助词「は」和「が」的认识关于日语头部身体词汇惯用句论网络对日语学习的影响关于中日同形词差异的研究关于的「の」用法关于现代日语中的推量表达关于日语中第一人称的省略表达日语被动句的考察论から与ので的异同关于日语中的女性用语1.关于日本现代流行语引言动漫是将漫画等平面的绘画采用电影原理制作形式将其表达出来,现在动漫产业的范围应经远远不止动画的这么简单。
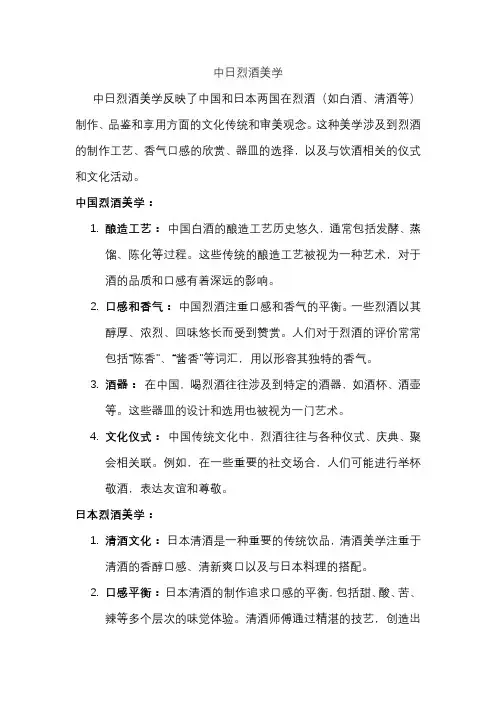
中日烈酒美学中日烈酒美学反映了中国和日本两国在烈酒(如白酒、清酒等)制作、品鉴和享用方面的文化传统和审美观念。
这种美学涉及到烈酒的制作工艺、香气口感的欣赏、器皿的选择,以及与饮酒相关的仪式和文化活动。
中国烈酒美学:1.酿造工艺:中国白酒的酿造工艺历史悠久,通常包括发酵、蒸馏、陈化等过程。
这些传统的酿造工艺被视为一种艺术,对于酒的品质和口感有着深远的影响。
2.口感和香气:中国烈酒注重口感和香气的平衡。
一些烈酒以其醇厚、浓烈、回味悠长而受到赞赏。
人们对于烈酒的评价常常包括“陈香”、“酱香”等词汇,用以形容其独特的香气。
3.酒器:在中国,喝烈酒往往涉及到特定的酒器,如酒杯、酒壶等。
这些器皿的设计和选用也被视为一门艺术。
4.文化仪式:中国传统文化中,烈酒往往与各种仪式、庆典、聚会相关联。
例如,在一些重要的社交场合,人们可能进行举杯敬酒,表达友谊和尊敬。
日本烈酒美学:1.清酒文化:日本清酒是一种重要的传统饮品,清酒美学注重于清酒的香醇口感、清新爽口以及与日本料理的搭配。
2.口感平衡:日本清酒的制作追求口感的平衡,包括甜、酸、苦、辣等多个层次的味觉体验。
清酒师傅通过精湛的技艺,创造出各类口感丰富的清酒。
3.杯器文化:类似于中国,日本也有独特的杯器文化。
不同形状和材质的杯子可能会影响清酒的味道和香气。
4.仪式感:在日本,清酒品尝往往带有一定的仪式感,包括倒酒、磕杯、举杯敬酒等礼仪,这强调了饮酒活动的庄重和仪式感。
总体而言,中日烈酒美学反映了两国深厚的酿酒传统、文化习惯以及对于烈酒品质和品味的独特追求。
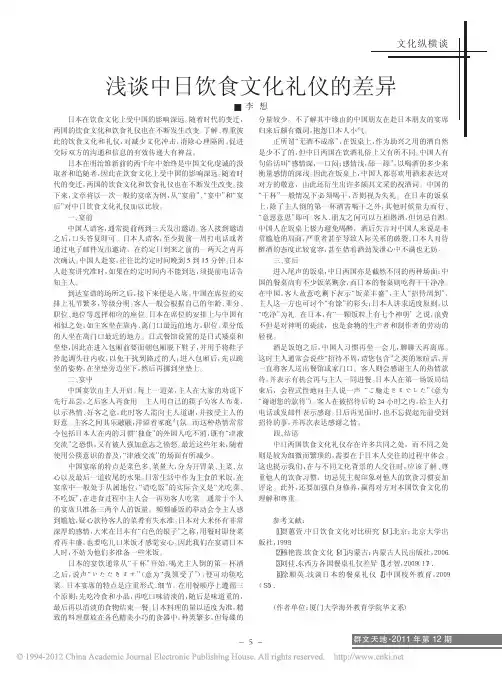
一、酒文化的起源在这大千世界中,我们生而为人。
从出生起我们就与周围的环境有了千丝万缕的联系。
就如同每天都要一日三餐一样,我们每天都在进行着各种各样的社交活动。
很少有人能够脱离群体单独生活行动,而在与他人交往的过程中,就需要用到一些社交手段。
而最常见的就是酒桌文化。
酒,是人类历史上一大伟大发明。
而根据大多数民族和国家的传说和考古显示,最早掌握酿酒技术的就是猴子。
它们采摘野果,吃不完就储存起来,于是剩下的果子发酵,就变成了酒。
酒被应用于各个方面。
度数低的酒,人们喝下去可以提高兴致缓和气氛;度数高的酒,可以被用作医疗方面,起到消毒杀菌的作用。
中国古代的文人墨客对酒更是爱不释手,酒是他们灵感的来源、感情的催化剂。
东晋有陶渊明,虽不为五斗米折腰,却在《五柳先生传》中说:“性嗜酒,家贫不能恒得”;苏轼嗜酒,所作诗词中也是酒气熏天;“三杯卯酒人径醉,一枕春眠日亭午”;就连我们的诗仙李太白也感叹“古来圣贤皆寂寞,惟有饮者留其名!”无论喜怒哀乐,以酒助兴或消愁绝不仅仅是我们中国人的专利。
二、日本酒的种类中国是世界上酒文化最早的发祥地之一,而与中国一衣带水的日本同样也为世界酒文化的发展史做出了不可磨灭的贡献。
在中国,我们有白酒。
而在日本酒文化里,常见的有清酒、烧酒和啤酒。
日本的酿酒技术来自中国,根据古书记载,日本古代是没有“清酒”的,但日本人不喜欢白酒那样烈性的酒,于是就在酒中加入了竹碳来过滤,从而发明了清酒和烧酒。
清酒和烧酒对于中国人来说比较陌生,但自古以来日本人喜欢清酒却是名不虚传。
清酒是用秋季收获的大米再经历一整个冬季发酵后酿造而成的。
清酒的度数是15~16度左右。
因为酒味可口甜美,可以冷喝也可以热喝,所以上到五星级的大酒店下到路边的小酒馆都有清酒的身影出现。
清酒根据米的产地和水质分成了三六九等,但是无论是哪一种清酒,都是日本菜肴的绝佳搭配。
一瓶酒的好坏不仅取决于酿酒的大米,更是取决于酿酒所用的水。
在2015年掀起的“日本酒热潮”的“第一酒”就是由一家位于日本本州西部的山口县的一家小厂酿造的。
从谚语看中日酒文化的异同性王磊;王瑶;刘海玉;盛亚飞;张晓莹;王胜男【摘要】Language is the carrier of culture. Proverbs, as a kind of language expressions, also contain a wealth of culture. Liquor culture in both China and Japan has a long history, and Chinese and Japanese have created many popular and liquor-related proverbs in the development of liquor culture. Those liquor-related proverbs in two countries have reflected their features of liquor culture and they not only have their own unique national characteristics but also have the similar features.%语言是文化的载体,谚语作为语言的一种,亦包含丰富的文化。
中日酒文化源远流长,在酒文化的发展过程中,两国人民创造出许多脍炙人口、流传至今的酒谚语。
这些酒谚语所折射出的中日两国的酒文化,既各具民族特色,又有相似之处。
【期刊名称】《酿酒科技》【年(卷),期】2015(000)006【总页数】3页(P103-105)【关键词】酒文化;谚语;中日对比【作者】王磊;王瑶;刘海玉;盛亚飞;张晓莹;王胜男【作者单位】河南师范大学外国语学院,河南新乡453007;河南师范大学外国语学院,河南新乡453007;河南师范大学外国语学院,河南新乡453007;河南师范大学外国语学院,河南新乡453007;河南师范大学外国语学院,河南新乡453007;河南师范大学外国语学院,河南新乡453007【正文语种】中文【中图分类】TS971自古以来,中日文化的交流史源远流长,但由于生活习俗、文化背景、传统文化、价值观念、思维方式和社会规范等不同,中日两国的酒文化呈现出丰富多彩的民族特色。
从饮酒看中日文化的差异酒是朋友间交流的润滑剂,不熟悉的人之间通过喝酒交流情感,也可以增进友谊,成为朋友。
工作中与同事之间的交往过程中酒是必不可少的,而与客户交流和应酬过程中也少不了酒的存在。
随着中国经济的发展,对外开放的脚步越来越大,与外国人的交流也是司空见惯的事情,就饮酒而言不同国家饮酒习惯也不同。
今天笔者带您了解一下日本饮酒文化的趣事。
在日本家中冰箱里常备的酒类就是啤酒,日本人不管男女下班回家后,打开冰箱就喝一杯啤酒,因此日本人更喜欢把啤酒当成了饮料,在喝啤酒方面日本人酒量可不小。
另外,在日本除了喝茶外,日本人一般不喝热水,打开水龙头就用杯子喝凉水,所以在家喝点啤酒就当喝水了,不过在家自己喝啤酒肯定不会贪杯,差不多就行了。
下面我们就说说日本人如何与人应酬。
一、日本人口喊“干杯”却不一定干杯首先日本人聚会非常守时,比如说晚上6点一起吃饭,一般会提前10分钟左右到达制定地点,太早或太晚都不太好。
等全部人员都到齐后,大家点菜吃饭,点菜过程中人们一般会客随主便,所点菜肴多为套餐或菜肴分餐,所以每个日本人面前大盘子、小碟子很多,日本人一般不会一起吃一盘菜,除非到中餐馆。
等上菜后,日本人就一起喊干杯(乾杯、かんぱい),这里大家请注意,日本人的干杯跟我们不同,我们喝啤酒的习惯是第一杯一饮而尽才算有诚意,也有敬意,所谓“先干为敬”就是我们的习惯。
如果大家都喝干了,有一个人没喝就感觉这个人不够意思了。
日本人的习惯是不喜欢勉强别人,所以即使大家一起喊“干杯”,也就是碰一下杯子意思一下而已,喝酒也是多少随意。
如果遇见对方比你年长或是你公司的上级,碰杯时你的杯子比他低一点就表示敬意了。
日本人特别偏爱啤酒,对啤酒也有很多要求,无论在家还是聚会都喝凉啤酒(冷やしたビール),所以日本人在家会在冰箱常备啤酒,去酒店店家也是常备凉啤酒,日本人认为凉啤酒喝了才有味道,常温啤酒喝不出啤酒的感觉,他们在喝完啤酒后才会换其他酒再喝。
酒与酒文化的学习研究报告摘要:酒是一种古老的饮料,自古以来在全球范围内有着广泛的应用和深厚的文化背景。
本报告旨在探讨酒与酒文化的学习和研究,包括酒的历史和种类、酒的制作工艺、酒的文化和社会影响等方面的内容。
通过对相关文献的综述和分析,我们得出了一些重要结论,为进一步研究和学习酒与酒文化提供了基础。
1. 引言酒作为一种饮料,自古以来在各个文化中扮演了重要的角色。
它不仅是一种享受,还与社交、仪式、宗教和医药等方面密切相关。
因此,对酒及其文化的研究具有重要意义。
2. 酒的历史和种类酒的历史可以追溯到数千年前,各个地区和文化都有自己独特的酿酒传统和酒种类。
常见的酒种类包括葡萄酒、啤酒、烈酒等,每种酒都有其独特的制作工艺和口感。
3. 酒的制作工艺各种酒的制作工艺各不相同,但总的来说,包括发酵、蒸馏、贮存等环节。
不同的酒制作工艺决定了酒的口感和品质。
4. 酒的文化和社会影响酒文化是各个地区和民族特有的文化现象,它反映了人们的生活方式、价值观和社会关系。
酒在社交、仪式、宴会等方面起到了重要的作用,也对社会经济产生了一定影响。
5. 酒与健康除了享受和文化的层面,酒对健康也有一定的影响。
适量的饮酒被认为对心血管系统和一些疾病有益,但过量饮酒则会对健康产生负面影响。
6. 结论酒与酒文化的学习和研究具有重要意义,有助于增进对酒的了解和酒文化的传承。
同时,我们也应当注意适度饮酒的原则,将酒文化发展为一种健康的生活方式。
综上所述,酒与酒文化的学习和研究是一项复杂而有意义的任务,它涉及到历史、文化、制作工艺、社会影响等多个方面。
通过不断深入研究和学习,我们可以更好地理解和欣赏酒的博大精深。
中文提要酒文化无论在哪个国家的风俗中都占有非常重要和特殊的地位。
中日两国是一衣带水的邻邦,同属东方民族。
两国从古代就开始了交流,日本从中国学习技术的同时也吸收了中国的文化,在各方面有相似的生活方式以及文化。
其中酒文化也出自同一渊源,中国的传统文化、农业文明和曲酒酿造技术传到日本,促进了日本文化及酒业的发展。
中日两国的酒文化历史、酒俗、饮酒态度和酒德酒礼都大同小异,各有所长,各有所短。
中日两国人民相互交流,相互学习和借鉴,在差别中寻求融合,在融合中保存差别,共同创建适合于本国国情和世界酒文化发展方向的新型酒文化。
本文以中日两国的酒文化为研究对象,进行展开论述,本文首先从世界酒的起源,中日两国酒文化的起源,发展,特征等方面详细说明,接着从中日两国酒文化的多个方面,例如酒的种类,喝法的差异,饮酒礼仪等方面,对中日两国的酒文化进行详细的分析,最后通过对两国酒文化的比较,总结出两国酒文化的差异。
关键词:中日酒文化交流发展外文提要酒文化はどのような国の習慣においても重要な地位を占める。
両国の距離が近く,一衣带水の国である。
両国は古代からさまざまな交流がはじまり、日本は中国からの技術を勉強するとともに、中国の文化を吸収し、各方面に似ている生活方式と文化がある。
その中の酒文化が同じ根源であり、中国の伝統的な文化、農業文明および醸造技術は日本につたわり、日本文化と酒造の発展を促進した。
中日の酒文化史、飲酒の習俗、酒に対する態度と飲酒の礼儀作法は大同小異であり、それぞれの長所と短所がある。
中日の国民はお互いに交流し、勉強し、差異の中に共通処を見つけ出しながら、自分の特色を保つ。
共同で自国文化と世界酒文化の発展に適する新型酒文化を創ろうとしている。
本稿は中日酒文化を研究対象にして検討し、先ずは世界酒の起原と中日の酒文化の起原、発展、特徴などから説明する。
それで、中日酒文化の各方面から、たとえば、酒の種類とか飲む方法の異同とか礼儀などの方面から中日酒文化を詳しく分析する。
最後に両国酒文化の比較することを通じて両国の酒文化を総括する。
キーワード:中日酒文化差異交流発展目次はじめに (1)第1章酒の始まりと歴史と発展過程 (3)1酒の始まり (3)2中国の酒の歴史と発展過程 (2)3日本の酒の歴史と発展過程 (3)第2章中日酒文化の共同点 (5)第3章中日酒文化の違う点 (5)1酒の種類について (5)2飲み方と飲む礼儀について (6)2.1乾杯の意味 (6)2.2「絶対ぜったいに酔すいっ払ぱらってはならない」というタブー (6)2.3「宴会でまじめな話をしてはならない」というタブー (7)2.4 酒を勧める時の習慣 (9)3 祭りについて (9)4 婚俗こんぞくについて (9)5 ほかにのついて (10)6 結論 (10)おわりに (11)注 (12)参考文献 (13)はじめに日本にほんは,中国ちゅうごくの近ちかくに位置いちしている。
両国りょうこくは古代こだいから交流こうりゅうしてきた。
日本にほんは中国ちゅうごくから技術ぎじゅつを習ならうのと同時どうじに、中国の文化もならってきた。
それが故ゆえ、各方面で,類似的るいじてきな生活様式や文化を持っている。
中国も日本も酒の国と称されている。
酒文化は悠久な歴史を持つている#中国には「日に一杯の酒を飲めば、99歲まで生きられる」という諺もある。
長年来、日本をよく理解するために、いろいろな面から研究した文章が発表されている。
例えば、彭広陸氏の『日本料理名の比較』、潘鈞氏の『日本人の漢字観の変化』などの文章がある。
本稿ほんこうでは、酒文化さけぶんかの面から日本を研究する試みをした。
日本は自分の民族性があるので、自分の文化をもっている。
それが故、各方面で類似的な生活様式や文化を持つているが、その反面、乾杯と酔つ払いに対しての見方や、宴会などでのまじめな話しについての観念の面では大きな相違点も見受けられる。
中日酒文化の共通点や違う点を研究して、日本社会をよく理解することに役立ちたい。
1第1章酒の始まりと歴史と発展過程1 酒の始まり12億年前というはるかな昔この地球に、酒を造る酵母菌こうぼきんの先祖があらわれたのに続いてほぼ20万年前、人間(ホモサピエンス)が出現したが、その頃には、酵母はすでに大きな進化をとげ、糖とうを発酵はっこうしてゕルコールを造る機能をもつようになったと思われる。
その酵母が、地上に落ち、果物を自然に繁殖はんしょくさせ、果物を発酵させた。
その後、人類は作物を栽培さいばいし収穫しゅうかくすることをおぼえ、その貴重きちょうな食べ物と、目に見えない酵母を巧たくみにあやつって、酒をつくりあげた。
もちろん、まだ酵母の存在さえしらず、その概念ももたなかった当時の人々は、この発酵という不可解な現象を、すべて「神のなせるわざ」だと考えたに違いない。
「古い文明は必ずうるわしい酒を持つ。
すぐれた文化のみが、人間の感覚を洗練し、美化し、豊富にすることができるからである」[1]といわれる通り、世界の民族は、独自の酒とその文化を育ててきた。
それが民族間の交流によって各地へ伝播でんぱされ、時代とともに改良かいりょうされ、進歩してきた。
たとえば、メソポタミゕで始まったワンは、シュメール人、フェニキゕ人、ギリシゕ人、ローマ人の手をへて、穀物こくもつにはあまり適さないが果樹かじゅには良いという自然を背景にヨーロッパ全土に展開し、発展してきた。
2 中国の酒の歴史と発展過程中国の酒造りの歴史は大変古く、2004年に、「今から9000年ほど前の賈湖遺跡で酒造りの痕跡を見つけた」という発見があり、世界を驚かせた。
歴史時代では殷(商)の王(今から約3100年前)が宮廷に3000 人を収容できる「酒池肉林」を造つたという有名な逸話もある。
秦の始皇帝、2漢の武帝も造営した。
今から1800年前の『三国志』の時代には西域から葡萄酒が多く入つてきた。
この時代では曹操の禁酒令、孫権の酒乱なと、酒の話題が大変になつた。
6世紀の北魏時代、現存する最古の料理害『斉民要術』が著され、さまざまなお酒の造り方が細かく残された。
また、ニの頃には度数の高い酒も登場していたようで、「匂いを嗅ぐだけで何日も昏睡した』という話もある。
8世紀の唐下朝の時代、多くのお酒に関する漢詩が詠まれた。
中でも、西域の砂漠を舞台とする「边塞詩」ではお酒を情緒深く络ませている。
11世紀頃の宋代になると、蒸留酒であるむ酒が多く造られるようになり、現在に至つている。
中国の蒸留酒の始まりについてはあまり分かつていない。
現在では各都市で1万を超える地の白酒が造られるなと、中国人にとつて身近なお酒になつている。
今から100年ばと前、ドツが中国の山東半島へ進出した時、ここにビールとワンの製造工場を造つた。
このため、現在でも中国山東省ではビールとワンの生産が盛んである,今日、中国を代表する高級白酒は五粮液である。
3 日本の酒の歴史と発展過程日本の酒は土着の酒と、渡来人が伝えた酒の2種類が知られている。
土着の酒については米を嚙んで吐き溜める[ロ嚙み酒]が知られ、「醸す」という読みは[喃む」が語源になつたという説がある,一方、渡来人が伝えた酒は現在の「甘酒」にあたる酒と考えられている。
これは麹を原料とした醸造法で、大王の一族が朝鮮半島から技術者を連れてきたのが始まりという。
古代日本のお酒は朝廷の造酒司を中心に更なる開発.改良が進められており、平安時代中頃の10世紀には現在のような日本酒の醸造法が確立し3ていた。
平安末期、朝廷が衰えると酒造りの技術は大阪,奈良なとの大寺院が受け縦ぎ、「僧坊酒」として名を博す。
戦闲末期、津島にもゆかりのある織田信長はこれらの寺院に対して徹底的に弾炻を加えた。
これにより僧坊酒の高度な技術は流出、分散し、各地で地酒が造られる下地になつた。
今から約600年前の1404年、長崎県に、朝鮮半島からゕルル度数の強い蒸留酒が送られてきた,これが日本で最初に確認できる焼酎である。
その後、琉球からも泡盛の製法が伝来し、焼射は九州各地で造られるようになつた。
今から6年前、焼酎は突如ブームとなり、多くの銘枘を見かけるようになつた。
豊臣秀吉は最晩年(1598年)、京都の醍醐寺で盛大な花見を催し、全国から銘酒も集めた。
ただし、これらの銘酒は現在でははとんど残っていない。
江戸時代初期、それまで年5冋醸造していた日本酒造りを幕府が「年1回冬期のみ]の醸造に制限した。
これは現在の酒造りにも继承されている。
明治以降(こなると、酒造業は製法も設備も近代化し、安定、安全に生産がで3るようになった。
今から約400年前、醍醐寺に博多の練貫酒、大阪の天野酒、伊豆の江川酒、備後の三原酒なと、各地から銘酒が集められたという。
第2章中日酒文化の共同点日本は,中国と非常に近い。
両国は古代から交流してきた。
また、儒学じゅがくの影響で、酒文化はいろいろな共同点を持っている。
両国の人民は酒が大好きだ。
酒についての文章もたくさんある。
例えば、中国三国時代の曹操そうそうの『短歌行たんかぎょう』がある。
日本の「万葉集」に書かれた山上憶良やまのうえのおくらの有名な「貧窮問答歌ひんきゅうもんどうか」の一節ひとふしに「堅塩けんしおをとりつづしろひ、糟湯酒かすゆざけうちすすろいて...」と、塩をさかなに酒糟を湯でといて飲む庶4民の姿が歌われていて、当時すでに貴族たちは「もろみ」を絞った「澄酒(すみざけ)」を飲んでいたことが伺える。
酒が祭祀さいしに役に立つことは明瞭めいりょうである。
両国とも酒で祭祀をする。
酒は神と人間との掛け橋として、神かみに捧ささげる。
そのほか、両国では、料理を作る時、よく酒を使う。
中国では黄酒を使い、日本では味醂みりんを使う。
第3章中日酒文化の違う点中日の酒文化は共同点がたくさんある。
しかし、あでやかな日本の風土とデリケートな日本人の感性とによって自分の酒文化が育てられ、発達してきた。
1酒の種類について中国の酒は大きくいって白酒しろざけと老酒らおちゅうに分かれる。
色で分類するのはいかにも即物的そくぶつてきだが、「白」は白色ではなく無色透明むしょくとうめいの意いで蒸留酒じょうりゅうしゅのことだ。
有名なものには「マオタ酒」(53度)をはじめ「五粮液ごかてえき」(60度)「汾酒ふんさけ」(50~60度)などがある。
黄酒きざけは醸造酒じょうぞうしゅでコハク色から得た名前であろう。
これは老酒とも言う。
よく熟成じゅくせいしたという意味から来たものらしい。
なかでも紹興酒しょうこうしゅ(13~18度ど)が有名ゆうめいだ。
黄酒きざけは地域的には長江以南が多いようだ。